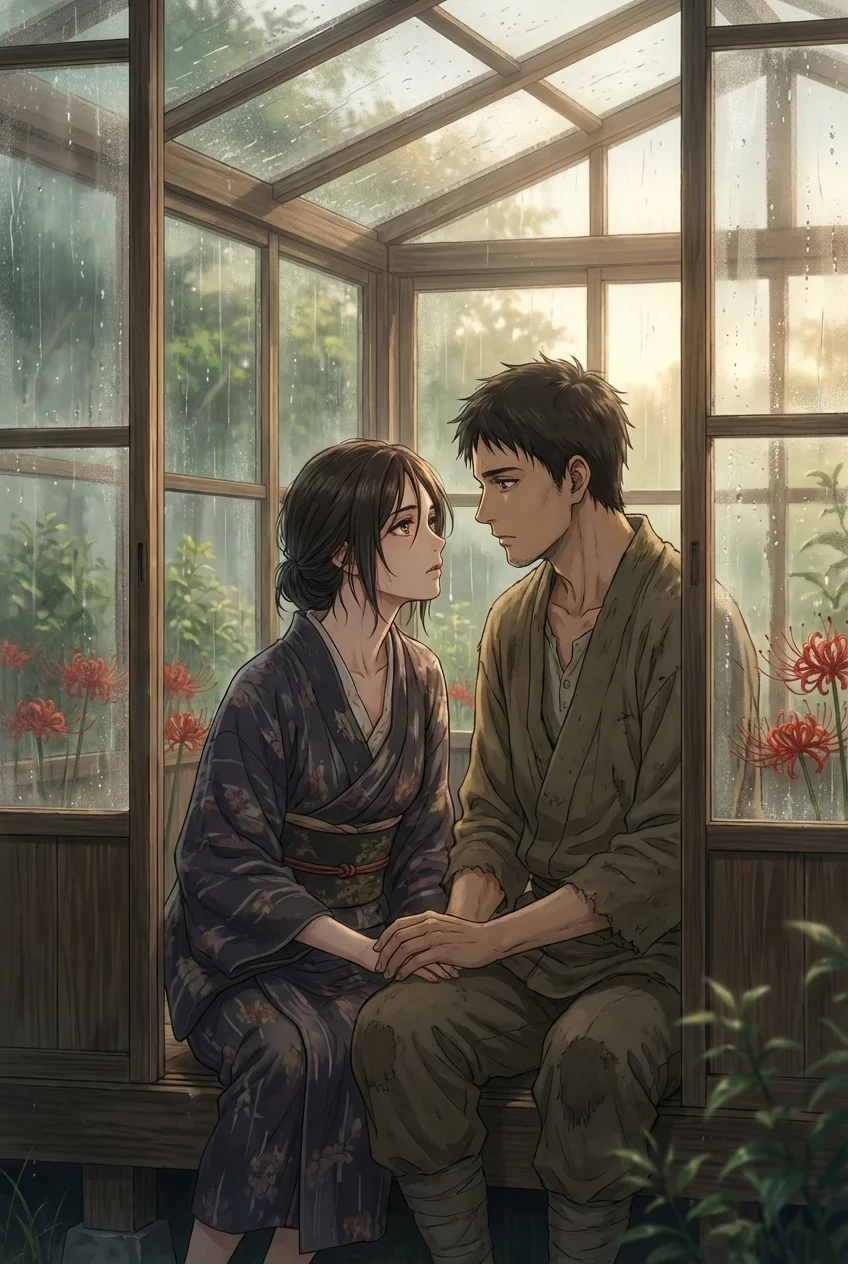第一章 硝子越しの視線
午後三時。高層ビルの最上階に位置する執行役員室は、恐ろしいほどの静寂に包まれていた。
壁一面のガラス窓からは東京の街並みが一望できるが、今の私、佐伯エミにとっては、その絶景も自らを閉じ込める檻の柵にしか見えない。
「……それで、先方の提示条件は?」
革張りのチェアに深く腰掛けた男――工藤玲也が、冷ややかな低音を響かせる。
私のボスであり、この会社で最も冷徹と噂される執行役員。整いすぎた顔立ちは彫刻のように無機質で、その瞳の奥には常に他人を見下すような鋭い光が宿っている。
「は、はい。北米支社の回答によれば、来期の予算承認を前提として……」
震える指先でタブレットを操作しながら、私は必死に声を絞り出した。
平常心を装おうとしているが、すでに限界が近い。
なぜなら、私の身体は今、デスクという絶対的な死角の下で、あり得ない状況に晒されているからだ。
工藤は、上半身だけは完璧なビジネスマンの顔をしている。
眉一つ動かさず、モニターに映る海外クライアントと流暢な英語で議論を交わしている。
けれど、そのデスクの下。
彼の長い脚の間にひざまずかされた私は、逃げ場のない熱に浮かされていた。
「Emi, hand me the file.(エミ、ファイルを)」
画面の向こうの相手に気づかれぬよう、彼は短く命じる。
私は足元の絨毯に膝をついたまま、震える手で書類をデスクの上に滑らせた。
その瞬間、書類を受け取ると同時に、彼の手がデスクの下へと伸びてくる。
「っ……!」
喉の奥で悲鳴が暴れた。
彼の大きく冷たい掌が、私のブラウスの襟元を乱暴に掴み、そのまま首筋へと這い上がってきたからだ。
「……静かに。マイクはオンだぞ」
視線すら合わせず、彼は英語で交渉を続けながら、日本語で残酷に囁く。
これは罰だ。
今朝、私が他部署の男性社員と笑って話していたことへの、陰湿で、とろけるほど甘美な制裁。
第二章 デスク下の秘密
工藤の指先は、まるでピアノの鍵盤を叩くように、私の敏感な箇所を正確に探し当てていく。
「Regarding the sheer market share...(市場シェアに関しては……)」
冷静な声色とは裏腹に、私に触れる手つきは執拗で、熱を帯びていた。
タイトスカートの裾から忍び込んだ指が、太腿の内側をゆっくりとなぞり上げる。
ストッキングごしの摩擦が、脳髄を痺れさせるような電気信号となって駆け巡った。
(だめ、声が出ちゃう……っ)
私は自分の口元を両手で強く押さえ、必死に嗚咽を堪える。
すぐそこのモニターには、数千キロ離れたビジネスパートナーたちの顔が並んでいるのだ。
もし今、私が声を上げてしまえば。あるいは、工藤がカメラのアングルをほんの少し下にずらせば。
私の社会的な地位は、一瞬にして崩壊する。
その極限のスリルが、恐怖を上回る興奮となって、下腹の奥をきゅんきゅんと締め付けた。
理性が焼き切れる音が聞こえる。
「んぅ……っ」
工藤の指が、一番触れてほしくない、けれど待ち望んでいた秘めやかな場所に到達した。
あえて直接触れるのではなく、下着のレース越しに、焦らすように円を描く。
じわり、と熱い雫が溢れるのが自分でも分かった。
羞恥で顔が沸騰しそうだ。
こんな、仕事中に。上司のデスクの下で、あられもない姿になって濡れているなんて。
工藤は意地悪だ。
私の反応を指先で感じ取っているくせに、画面の向こうへ向けて涼しい顔で頷いている。
「I see. However...(なるほど。しかし……)」
彼の言葉が途切れるタイミングで、意図的に指に力が込められる。
「ひっ……!」
声にならない息が漏れた。
ビクン、と腰が勝手に跳ねる。
逃げようとする私の腰を、彼のもう片方の手が太腿を掴んで固定する。
(お願い、許して……もう、おかしくなる)
懇願するように見上げると、一瞬だけ、工藤が私を見下ろした。
その瞳は、獲物を追い詰める捕食者のように暗く濁り、それでいて背筋が凍るほど美しかった。
彼は口パクでこう告げた。
『我慢しろ。イくときは許可制だ』
その絶対的な命令が、私の最後の理性を粉々に砕いた。
第三章 決壊する理性
生殺しの時間が続く。
工藤の指は、熟れた果実を愛でるように、執拗に私の最奥を弄ぶ。
強弱のリズム。
会議の議論が白熱し、彼の口調が強くなると同時に、指の動きも激しさを増していく。
カリカリと爪先で敏感な突起を掠められたかと思えば、掌全体でぐっと押し込まれる重圧感。
そのたびに、私の身体は快楽の波に飲み込まれ、視界が白く明滅した。
(あ、あつい……もう、むり……)
全身の血が逆流するような感覚。
頭の中が真っ白になり、仕事も、プライドも、羞恥心も、すべてが快楽の濁流に押し流されていく。
彼の手が、ついに下着の縁をかき分け、直接その濡れた花弁に触れた瞬間。
「……っ!?」
私の身体は弓なりに反り返り、無言の絶叫を上げた。
声を出してはいけない。
その一点だけで繋ぎ止められていた意識が、弾けるように飛散する。
工藤の指が、ぬるりとした愛液を絡め取りながら、奥深くにある柔らかい壁を突き上げた。
「んぐっ、ぁ、ぁあ……ッ!」
私の口を塞いでいた手など役に立たず、喉の奥から甘い声が漏れ出しそうになる。
けれど、その瞬間。
「Well, let's conclude this meeting.(では、会議はこれで)」
工藤が素早くマイクをミュートにし、同時にカメラを切った。
プツン、という電子音と共に、世界は私たち二人だけのものになる。
「……よく我慢したな」
彼がデスクの下を覗き込む。
そこには、乱れた衣服と、涙目で荒い息を吐き、快楽に蕩けきった無様な私の姿があった。
「工藤、さん……ひどい……」
涙ながらに抗議する私の顎を、彼は濡れたままの指先で掬い上げる。
その指には、私自身の興奮の証が、糸を引くほどたっぷりと付着していた。
「ひどい? 身体はこんなに正直に喜んでいるのにか」
彼は嗜虐的な笑みを浮かべ、その指を私の唇に押し付けた。
「綺麗にしてくれ。……会議は終わったが、俺たちの打ち合わせはこれからだろ?」
逃げ場など最初からなかったのだ。
私は震える舌で、自らの蜜の味がする彼の指を舐め取った。
硝子の檻の中で、冷徹な王による甘く激しい独占劇は、まだ始まったばかりだった。