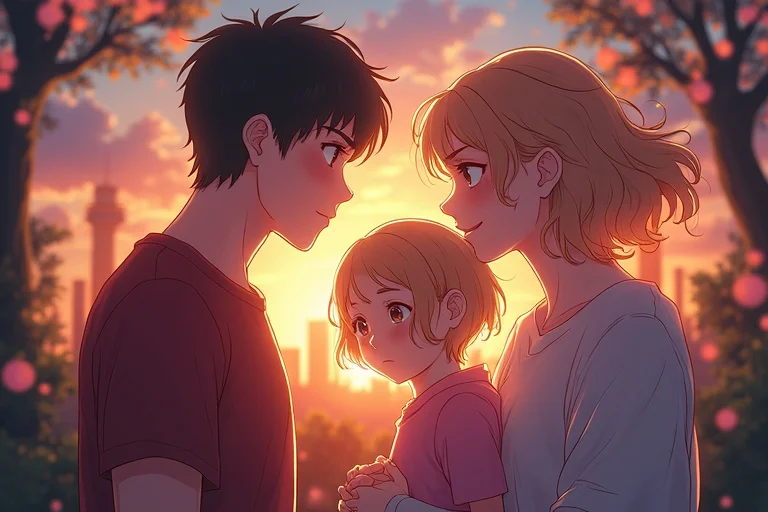第一章 沈黙と冷や汗のパレード
「でさあ、布団が吹っ飛んだってわけ! ギャハハ!」
満員電車。隣の男が喚いた。
瞬間、僕の視神経がジャックされる。
網膜の裏側で、羽毛布団が高解像度4Kで離陸した。
ジェットエンジンの轟音。
成層圏へ突き進む西川ブランドのロゴ。
はためくシーツの風切り音までが、ドルビーサラウンドで脳髄を揺らす。
(やめろ。再生するな)
吊革を握る右手が痙攣する。
掌の汗が革を濡らし、不快な音を立てて滑った。
胃の腑から込み上げる熱い塊を、歯を食いしばって押し戻す。
ここで笑えば、トリガーが引かれる。
だが、脳内の布団は無慈悲にも大気圏を突破。
摩擦熱で炎を纏いながら、美しく燃え尽きた。
「……ッ、プ」
鼻から空気が漏れた。
ゴゴゴゴゴ……!
直後、車両が跳ねる。
窓の外、アスファルトを突き破り、マンホールから一万個の極彩色の風船が噴き出した。
破裂音。ゴムの匂い。
信号待ちのトラックが、風船の浮力でゆっくりと宙へ浮いていく。
「うわ、またかよ」
「マジ迷惑」
乗客が一斉にスマホを向ける。
レンズ越しに見る世界は冷めている。
誰も笑わない。
ただ「現象」として消費するだけ。
僕のポケットで、計測器が短く震えた。
数値は「3.2」。
低い。
この程度のカオスでは、世界の上書きには程遠い。
僕は脂汗を袖で乱暴に拭い、ドアが開くと同時にホームへ転がり出た。
第二章 数式に取り憑かれた男
駅前広場の気温が、ふいに五度下がった気がした。
雑踏が割れる。
その男の周囲だけ、誰もいない。
純白のスーツ。
磨き上げられた革靴。
そして、人工物めいて整いすぎた、白すぎる歯。
男は無言で僕の前に立ち塞がった。
手には、禍々しい赤色灯を点滅させる計測器。
(なんだ、こいつは)
男が口を開く。
カチリ、と入れ歯が噛み合うような硬質な音がした。
「計算が合わない」
抑揚のない声。
彼は懐から一枚のフリップを取り出し、機械的な動作で僕に見せつけた。
『 アルミ缶の上にあるみかん 』
フォントは明朝体。
余白のバランスが完璧すぎて、逆に気味が悪い。
瞬間、僕の脳がバグる。
広大な雪原。
その中心に鎮座する巨大なアルミ缶。
上に乗ったみかんが、幾何学的な回転をしながら、虚無の歌を歌い始める。
(寒い)
物理的な冷気が背筋を駆け上がる。
シベリアの寒風。
凍てつくツンドラの匂い。
面白くない。
まったく面白くないのに、脳内の映像出力が最大値を振り切る。
「……ッ、ぐぅ!」
「君の反応係数は異常だ」
男が二枚目のフリップをめくる。
周囲の女子高生が、汚物を見る目で彼を避け、足早に去っていく。
街路樹の葉が、一瞬で枯れ落ちた。
こいつだ。
世界から「笑い」を奪い、代わりにこの「絶対零度の不快感」を撒き散らしている元凶は。
第三章 カオス・オーケストラ
フリップがめくられるたび、精神が削られる。
『 電話に誰もでんわ 』
『 猫が寝込んだ 』
(やめろ……!)
脳内スクリーンで上映される、B級以下の惨劇。
受話器を持ったまま凍死する人々。
ベッドで点滴を受けるリアルな猫の断末魔。
論理と計算で組み上げられた「寒さ」が、鋭利な刃物となって神経を切り刻む。
膝が笑う。
意識がホワイトアウトしかけた、その時。
ドクン。
心臓が跳ねた。
限界を超えた圧力が、記憶の蓋を吹き飛ばす。
――あひゃひゃひゃ! お前バカじゃねーの!
誰かの声。
深夜のファミレス、ドリンクバーの安っぽい味。
教室の隅で回し読みした漫画。
文化祭、舞台袖で嗅いだ埃と、友人の緊張した汗の匂い。
テレビの前で腹を抱え、呼吸困難になるほど笑い転げた、あの熱狂。
理屈じゃない。
計算でもない。
ただ、どうしようもなく「面白かった」日々の残像。
「……ふざ、けるな」
僕は顔を上げる。
体中の血管が脈打ち、沸騰した血液が脳へ駆け巡る。
「笑いは……計算式なんかで、縛れるもんかよ!!」
思考のダムが決壊した。
僕の脳内で、最強の芸人たちが立ち上がる。
男の寒いダジャレに対し、一斉にツッコミの集中砲火を浴びせかけた。
『なんでやねん!』
『欧米か!』
『やかましいわ!』
ハリセンが唸る。
パイが飛ぶ。
金ダライが物理法則を無視して降り注ぐ。
そのカオスな映像エネルギーを、僕は眼前の白い男へ叩きつけた。
「な、……計測不能!?」
男の計測器が赤く発光し、高音を撒き散らす。
パァァァァァン!!
機械が爆散した。
同時に、僕の喉から、堰を切ったように爆笑がほとばしる。
それは感染した。
広場の人々へ、信号待ちのドライバーへ、街全体へ。
理性を吹き飛ばす、原初のエネルギーとして。
最終章 降ってきた平穏
世界が揺れた。
今度は、比喩ではない。
空がガラスのように砕け散り、巨大な影が落ちてくる。
「うわあああ! パフェだ! パフェが降ってきたぞおおお!!」
ズドオオォォォォン!!
ビルの屋上に、直径五十メートルのイチゴパフェが着陸した。
生クリームの甘ったるい匂いが、排気ガスを上書きしていく。
道路標識がグニャリと曲がり、知恵の輪になる。
サラリーマンの鞄から、数百羽の鳩が一斉に羽ばたく。
誰かが吹き出したコーヒーが虹になり、空にかかった。
「あははは! なんだこれ! めちゃくちゃだ!」
誰かが腹を抱える。
つられて、隣の人が涙を流して笑う。
あちこちで起きる爆笑の連鎖。
白い男は、へたり込んでいた。
その頭上直撃コースで、どこからともなく現れた金ダライが落下する。
ガァァァァァン!!
見事な音が鳴り響いた。
眼鏡がズレる。
整いすぎていた髪が乱れ、初めて人間らしい隙を見せた。
「……計算式に、『金ダライ』の変数は入っていなかった」
彼は眼鏡を直そうともせず、肩を震わせる。
その口角が、ククク、と吊り上がった。
「面白いじゃないか、君」
「……あなたも、意外といい音出しますね」
僕は荒い息を吐き、彼に手を差し伸べた。
男の手は、驚くほど熱かった。
空からはまだ、マシュマロや紙吹雪が降り注いでいる。
街はカオスだ。
明日には、空からタライではなく隕石が落ちてくるかもしれない。
「ま、それくらいが丁度いいか」
僕は空から降ってきたサクランボを一つキャッチし、口に放り込んだ。
甘酸っぱい味が、予測不能な日常の幕開けを告げた。