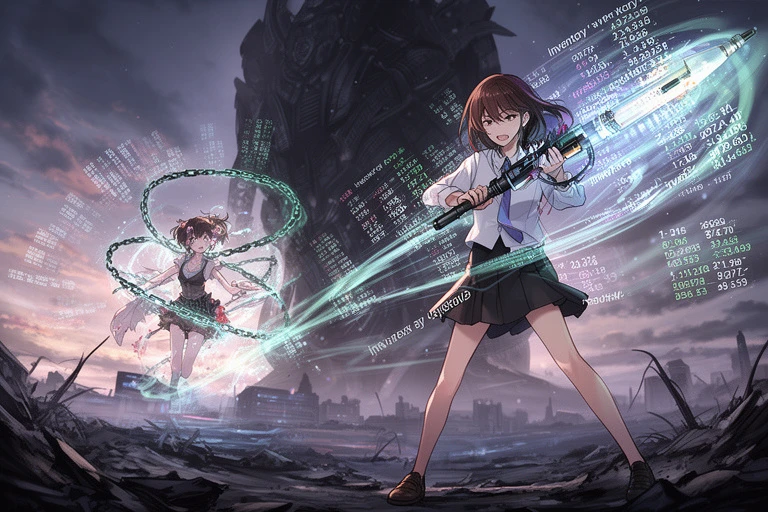第一章 午前二時の青白い救済
舌の上にへばりつくのは、泥のように煮詰まったコーヒーの酸味だ。
空調の切れたオフィスには、湿った書類と温まったプラスチック、そして男性社員たちの脂汗が混じった特有の臭いが沈殿している。頭上の蛍光灯が一灯だけ、チカチカと不規則に明滅しては、私の網膜を苛立たせた。
「佐倉、まだ終わらないのか。その集計表、セルの参照先がズレてるぞ」
背後から課長の声が降ってくる。タバコとミントガムが混ざった不快な呼気。私は反射的に肩を跳ねさせ、「申し訳ありません」と唇だけで動いた。
三十四歳、経理部。私の仕事は、他人が稼いだ数字を右から左へ流し込み、一円のズレもなく整列させること。そこには私の意志も、創造性も介在しない。ただ摩耗していくだけの部品だ。
午前二時半。終電はなく、タクシーで帰宅した安アパートの静寂だけが、私を許容していた。
クレンジングもせずベッドへ崩れ落ちる。強張った指先が、鎮痛剤を求めるようにスマートフォンの画面をなぞった。
『みんなー! 今夜も星空の下で会えたね、セラフィムだよ!』
六インチの画面の中、銀髪の歌姫が舞う。物理演算で制御された完璧なドレープ、ノイズの一切ないソプラノ。
彼女は、私の汚れた現実とは無縁の「聖域」だ。給与口座の残高が家賃ギリギリになろうとも、私は迷わず『スーパーエール』のボタンを連打した。画面を埋め尽くす金色の薔薇。彼女が私の名を呼ぶ。その一瞬の承認だけが、私の輪郭を繋ぎ止めていた。
だが、違和感は唐突に訪れた。
新曲のラスト、彼女が天を仰いで微笑む決めポーズ。
完璧なシンメトリーを描くはずの口角が、右側だけコンマ数ミリ、引き攣るように下がった。同時に、マイクを握る指先が白く変色するほど食い込んでいるのが、高解像度の画面越しに見えた。
「……計算が、合わない」
私は身を起こした。あれはプログラムされた「切なさ」の演出ではない。
以前、私が未払金リストの中に紛れ込んでいた架空請求を見つけ出した時と同じ、背筋が粟立つ感覚。
直後、彼女の瞳孔が微かに揺れ、視線がカメラのレンズではなく、その奥にある「何か」に怯えるように泳いだ。
「たす、けて」
音声データには乗らない、唇の動きだけのSOS。
その瞬間、私の左手で高熱を発したのは、スマートフォンではなく、指にはめていた限定グッズのリングだった。
網膜が焼け付くような閃光。オフィスの黴臭い空気とは違う、どこか金属的で冷ややかな風が、私の頬を叩いた。
第二章 虚飾の歌姫
目を開けると、そこは「帳簿」のように整然としすぎた世界だった。
水晶でできた幾何学的な樹木。グリッド線のように正確に配置された石畳。空には太陽の代わりに、巨大な黄金の天球儀が回っている。
美しいが、息が詰まる。埃ひとつ、塵ひとつない潔癖な空間。
「……招かれざる客ですね」
声の主は、私の記憶にあるデータよりも遥かに痩せて見えた。
ルミナ。この世界「ステラストリア」の象徴にして、私が崇拝するセラフィムの正体。
だが、今の彼女にアイドルの輝きはない。ドレスの裾は泥で汚れ、その足首には、黒いコールタールのような粘着質の影が鎖のように巻き付いている。
「貴女も、私を消費しに来たのですか?」
彼女の瞳は、まるで死んだ魚のように濁っていた。
私の職業病とも言える観察眼が、彼女の状態を瞬時に監査する。
荒れた唇、目の下の隈、小刻みに震える指先。これらは「過労」と「栄養失調」、そして「極度の精神的摩耗」の兆候だ。彼女を取り巻くこの美しい世界は、彼女という個体から生命力を吸い上げて維持される、粉飾決算の舞台に過ぎない。
「違う。私は……」
言いかけた時、石畳の向こうから金属音が響いた。
現れたのは、顔のない衛兵たち。彼らは一糸乱れぬ動きでこちらへ向かってくる。その動きには「迷い」も「個性」もなく、ただ排除というタスクを実行するプログラムのようだった。
「逃げてください」ルミナが掠れた声で言う。「『人間』の匂いがするものは、ここではバグとして処理される」
私は足元の黒い影が、彼女の膝まで這い上がっているのを見た。あれは、彼女自身の「諦念」が具現化した負債だ。このままでは、彼女はあの黒い影に飲み込まれ、完全に「モノ」として処理されてしまう。
私の推しが、私の生きる希望が、こんな無機質なシステムのエサになっていいはずがない。
衛兵たちが槍を構える。その切っ先が光った瞬間、私の脳内でスイッチが切り替わった。
恐怖はある。だが、それ以上に「不合理な数字」を見過ごせない憤りが勝った。
私はポケットを探る。そこにあったのは、もはや現実世界では無価値なガラクタ――いや、今この瞬間だけは、最強の武器となる「在庫」だった。
第三章 最前列の反逆者
私は走り出した。衛兵に向かってではない。彼らの進行ルートを垂直に横切るように。
衛兵たちの動きは規則的だ。まるで旧式のマクロのように、一定の周期で巡回と索敵を繰り返している。
「右、左、停止、二秒。……そこ!」
私はバッグから取り出した「高輝度ケミカルライト(ウルトラオレンジ)」をへし折った。
パキッという乾いた音が響き、強烈な橙色の光が溢れ出す。私はそれを、衛兵の進行方向とは逆、広場の彫像に向けて全力で投げつけた。
経理屋の私ができるのは、剣を振るうことではない。「リソース」を囮に使って、相手の注意という「コスト」を無駄遣いさせることだ。
衛兵たちの頭部が一斉にオレンジの光へ向く。そのタイムラグ、わずか四秒。
私はその隙にルミナのもとへ滑り込んだ。
「何をするの! 汚れるわよ!」
ルミナが拒絶の声を上げる。彼女の周囲を取り囲む黒い影が、威嚇するように鎌首をもたげた。
「来ないで! ファンなんでしょう? なら、綺麗なままの私を見ていなさいよ!」
彼女の叫びは、悲鳴に近かった。
幻滅されたくない。理想の偶像であり続けたい。その強迫観念が、彼女をこの牢獄に縛り付けている。
影が私の足元にも絡みつく。氷のように冷たく、重い。それは「身の程を知れ」と囁く、私自身の劣等感のようでもあった。
だが、私は構わずに彼女の手首を掴んだ。
華奢で、骨張っていて、温かい。モニター越しには決して触れられなかった、生身の体温。
「離して! こんなボロボロの姿、見られたくない……!」
「うるさい!」
私は叫んでいた。上司にも、親にも、誰にも上げたことのない大声で。
「綺麗なだけの人形なら、とっくに飽きてる! 私がここまで来たのは、あなたが完璧だからじゃない!」
私はもう一本のケミカルライトを折り、今度はそれを掲げて闇を照らした。
「あんたが、画面の向こうで必死に笑ってたからだ! 泣きそうなのを堪えて、それでも立ってたからだ! その計算高い笑顔の裏にある、泥臭い努力を見てたんだよ!」
ルミナの目が見開かれる。
私の言葉は、彼女への称賛であると同時に、私自身への懺悔でもあった。
第四章 推しから、私へ
黒い影が私たちを飲み込もうと渦を巻く。
ルミナは震えていた。「でも、私は弱い。貴女が思うような聖女じゃない。ただの、臆病で、誰かに愛されたいだけの……醜い子供なの」
「知ってる」
私は彼女の前に立ち、迫りくる衛兵と影を睨みつけた。
「私だって同じよ。会社じゃペコペコ頭を下げて、家ではカップ麺すすって、あんたに貢ぐことでしか自分の価値を感じられない。寂しくて、惨めで、どうしようもない女よ」
自分の恥部をさらけ出す言葉は、喉を焼くように痛い。
「私の部屋、ゴミだらけなの。あんたのグッズに埋もれて、足の踏み場もない。……笑えるでしょう?」
ルミナが息を呑む気配がした。
私は振り返らずに続ける。
「でもね、そんな最低な夜に、あんたの歌が聴こえると、明日も会社に行こうと思えた。あんたが『弱さ』を隠して戦ってる姿が、私の『弱さ』を支えてたの」
私はルミナの方を向き、彼女の震える両肩を掴んだ。
「完璧なアイドルなんていらない。私が推したいのは、泥だらけで足掻いてる、人間くさい『ルミナ』なんだよ!」
その言葉が落ちた瞬間、ルミナの瞳から大粒の雫がこぼれ落ちた。
それは美しいクリスタルの涙ではない。鼻水をすすり、顔をぐしゃぐしゃに歪めて流す、子供のような本物の涙だった。
「……うん、……うぅ……ッ」
彼女が泣き声を上げると同時に、足元の黒い影に亀裂が走った。
完璧であることを放棄した彼女から、眩いほどの光が噴き出す。それは人工的なステージライトではない。脈打つような、熱を帯びた生身の生命力。
その光は、絡みつく影を焼き切り、迫りくる衛兵たちをデータノイズへと還元していく。
「馬鹿ね……。ファンに、こんな顔見せるなんて」
ルミナは泣き笑いのような表情で、私の手を握り返した。その握力は強く、痛いほどだった。
「私の『一番恥ずかしいところ』、見られちゃった」
「お互い様でしょ」
光が世界を満たしていく。
私の指にあったリングが砕け散り、温かな粒子となって消えていくのが見えた。
別れの言葉はいらない。この掌に残る熱さと、彼女の不格好な泣き顔があれば、私はもう大丈夫だ。
最終章 誰もいないステージで
鼻をつくのは、またしても酸化したコーヒーの臭いだ。
コピー機の駆動音が、一定のリズムでフロアに響いている。
「……佐倉、聞いてるのか?」
課長の声。私は顔を上げた。
以前なら縮こまっていたその視線の先に、私は「人間」を見ていた。
充血した白目、ワイシャツの襟元の黄ばみ、そして焦りを含んだ瞳の揺らぎ。
彼は絶対的な権力者ではない。彼もまた、上からのノルマと部下のミスの板挟みで摩耗している、ただの疲れた中年男性に過ぎない。
「聞いています」
私の声は、驚くほど低く、落ち着いていた。
「そのデータの不整合ですが、先方の在庫評価法が変わった影響です。こちらの資料の三ページ目、注釈をご覧ください。計算は合っています」
私は修正した書類を、彼の手元に迷いなく置いた。
課長が目を白黒させ、言葉を詰まらせる。「あ、ああ……そうか。なら、いい」
席に戻り、キーボードに指を置く。
スマートフォンの通知ランプが光った。ニュースアプリの速報。『セラフィム、無期限活動休止。充電期間へ』。
記事には、彼女の直筆メッセージが添えられていた。
『もっと強くなって、自分の足で立つために。少しだけ時間をください』
ふ、と笑みが漏れる。
左手の薬指には、もうリングはない。けれど、あの時握り返された手の痛みが、確かな記憶として刻まれている。
私はカレンダーアプリを開いた。
給料日直後の『セラフィム生誕祭ガチャ』の予定を削除する。
代わりに、空いた週末の欄に『簿記一級試験・申し込み』と入力した。そしてもう一つ、『ずっと行きたかったイタリアンで、高いランチを食べる』とも。
誰かの輝きに縋るだけの夜は終わった。
私の人生という帳簿は、私が管理する。
損益も、負債も、資産も、すべて引き受けて、私は私という物語を黒字にしていくのだ。
私は背筋を伸ばし、エンターキーを強く叩いた。
乾いた打鍵音が、ファンファーレのようにオフィスに響き渡った。