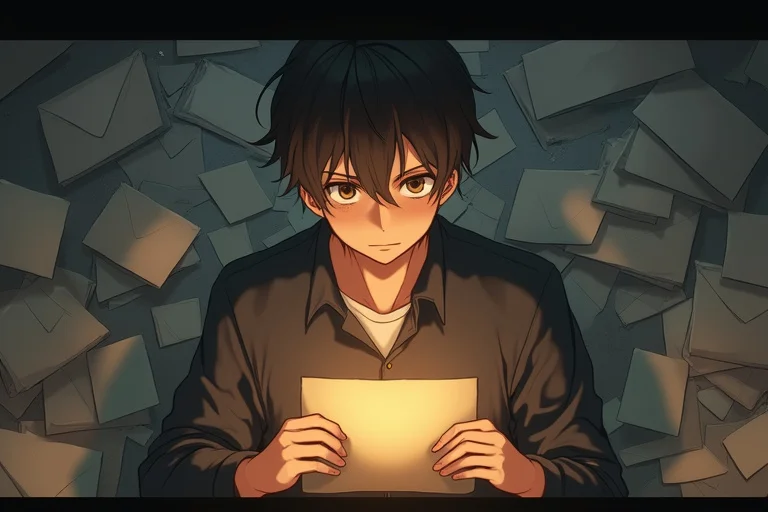「ねえ、時雨。その目、また『砂嵐』が降ってるんでしょ」
茜の声が、炉の熱気とともに鼓膜を打つ。
一三〇〇度の熱で溶かされたガラスの塊が、彼女の息吹ひとつで飴のように膨らんでいく。
工房には、焦げた鉱物と、甘いサイダーのような匂いが混ざり合っていた。
僕は作業台の冷たい感触を指先で確かめ、奥歯を噛みしめる。
「……いや。ただの眩暈(めまい)だ」
嘘だ。
視界の端が、テレビの放送終了後のような灰色に食い荒らされている。
僕の網膜は、物理的な光景と同時に、そこに付着した『残留思念』を強制的に焼き付ける。
普段なら、それは無害な残像だ。
子供が置き忘れたビー玉の輝きや、老人がベンチに残した溜息の跡。
けれど、今。
茜の背中にへばりついているソレは、質が違った。
彼女の輪郭が、ボロボロと崩れ落ちていく映像。
それは過去ではない。
これから数秒後、あるいは数分後に訪れる『確定した喪失』の予兆。
吐き気がした。
胃の腑(ふ)が雑巾のように絞り上げられる。
「隠しても無駄よ」
茜は吹き竿を回しながら、微かに笑う。
溶けたガラスが夕陽を孕んで輝く。
その光が網膜を焼くたび、僕の頭の中で不協和音が鳴り響く。
「時雨はいつも、自分だけ安全な場所にいて、そこから覗き込んでるだけ」
「……君こそ。その『砂時計』に、いつまで固執するんだ」
作業台の隅。
茜の祖父が遺した、未完成のオブジェ。
ガラスのくびれが歪(いびつ)で、砂が落ちない不良品。
「あと少しなの。おじいちゃんが言ってた。『これは時間を貯蔵する瓶だ』って」
茜の手が止まる。
その瞬間だった。
キィン、と耳鳴りがした。
茜の背後に浮かぶ灰色のノイズが、質量を持って膨れ上がる。
「え?」
茜の手から滑り落ちた吹き竿が、床に落ちない。
カラン、という音を立てるはずの金属棒が、空中でピタリと凝固している。
壁掛け時計の秒針が、痙攣したように逆回転を始めた。
重力の喪失。
時間の逆流。
僕の視界が真っ赤に染まる。
誰かの強烈な情念が、物理法則をねじ伏せようとしている。
目の前で、茜の左腕が透けた。
まるで最初からそこになかったかのように、背景のレンガ壁が透けて見える。
「――っ、茜!」
僕は叫び、彼女の手首を掴んだ。
触れた指先から、人間のものではない冷気が流れ込んでくる。
それは、死人の冷たさだった。
第二章 琥珀色の迷宮
「……時雨の手、震えてる」
時間の歪みが一時的に収束した工房で、茜は青ざめた唇で言った。
彼女の手の中には、あの砂時計が握られている。
「今の現象……ただ事じゃない。窓の外を見てくれ」
僕たちがいる工房の外。
いつもの路地裏の風景は消えていた。
代わりに広がっているのは、セピア色に褪せた、何十年も前の街並み。
古い都電が音もなく走り、モノクロの通行人たちが足早に通り過ぎていく。
過去と現在が、複雑骨折を起こしたように混線している。
「これ……おじいちゃんの記憶?」
茜が砂時計を差し出す。
ガラスの中で、琥珀色の砂が重力に逆らい、下から上へと昇っていた。
僕は砂時計に触れる。
指先から、電流のような痛みが脳髄へ突き抜けた。
――流れ込んでくる。
映像の濁流。
薄暗い部屋。
古時計の修理に没頭する背中。
『戻りたい』『やり直したい』という、ドロリとした渇望。
幼い頃の茜が、工房の隅で泣いている。
それを背中で聞きながら、祖父は狂ったようにガラスを研磨し続けている。
あの日、妻を救えなかった時間を、巻き戻すために。
(……逃げろ、茜。あの日と同じ過ちを繰り返すな)
脳内に響く声。
同時に、僕の視界――『心象視』が、残酷な答えを弾き出した。
茜の体が透明になっていく現象。
それは、祖父がかつて引き起こし、自らを飲み込んだ『存在消失』のプロセスそのものだった。
「……ッ、はあ、はあ」
僕は激しい動悸に膝をついた。
「時雨!?」
「わかったんだ。君の祖父は……事故で死んだんじゃない」
喉が張り付く。言葉にするのが怖い。
「強すぎる『未練』が、彼自身を時間の一部に変えてしまった。そして今、その歪んだ力が、血縁である君を『器』として取り込もうとしている」
茜の瞳が揺れる。
「おじいちゃんが、私を消そうとしてるの……?」
「悪意じゃない。純粋すぎる『愛着』だ。孤独な時間に、君という温もりを引きずり込もうとしている」
ゴゴゴ、と工房が軋む音を立てた。
空間の亀裂が広がる。
セピア色の街並みが、牙を剥いてこちらへ迫ってくる。
僕の目の前で、茜の足元が陽炎(かげろう)のように揺らぎ、消え始めた。
「嫌……足が、動かない。時雨、助けて」
彼女の声が上ずっている。
いつも気丈な彼女が、迷子のような目で僕を見つめている。
助けなきゃ。
わかっている。
けれど、僕の足もまた、恐怖で床に縫い付けられていた。
この力に干渉すれば、僕自身が無事では済まない。
今まで「見るだけ」で済ませてきた、傍観者の報いを受けることになる。
死ぬのが怖い。
君を失うのも怖い。
二つの恐怖が天秤に乗り、ギチギチと音を立てる。
(時雨はいつも、安全な場所から覗いてるだけ)
さっきの彼女の言葉が、胸に刺さった棘のように痛んだ。
僕は、歯が砕けるほど強く噛みしめ、一歩を踏み出す。
「離すなよ。僕が、引き剥がす」
第三章 砂の城、銀の雨
世界は融解していた。
工房の天井は剥がれ落ち、頭上には巨大な時計の歯車が回転する空が広がっている。
僕たちは、嵐のような砂粒の中、互いの手を握りしめていた。
「時雨、どうする気なの!?」
茜の体は、もう半分以上が透明になっていた。
僕が握っている手だけが、かろうじて彼女をこの世に繋ぎ止めている錨(いかり)だった。
「その砂時計を、僕に渡してくれ」
「駄目! これを持ったら、時雨が標的になる!」
「いいから!」
僕は怒鳴った。
そうでもしなければ、足がすくんで逃げ出しそうだったからだ。
「僕の『目』は、見るだけじゃない。視界に入れた『因果』を、自分に転写できる」
「嘘よ……そんなことしたら、時雨が消えちゃう」
「消えない! ……たぶん」
声が震える。
情けないほど、生への執着が湧き上がる。
明日の朝、君とコーヒーを飲みたかった。
来週の映画の約束も、まだ果たしていない。
読みかけの本も、書きかけの手紙も。
未練が、僕を現実に引き留めようとする。
けれど。
君のいない世界で生きる永遠よりも、君を生かす刹那の方が、今の僕には価値があった。
「茜。君が消える未来なんて、僕にはただの地獄だ」
「イヤよ! 私が助かるために時雨がいなくなるなんて、絶対にイヤ!」
茜が抵抗する。
透き通った涙が、頬を伝う前に光の粒になって散っていく。
その光景が、僕の決意を鋼に変えた。
「ごめん」
僕は強引に、彼女の手から砂時計を奪い取った。
ズシリ、と重い。
たかだか数百グラムのガラスの中に、一人の人間の人生が詰まっている。
「う、あぁぁぁぁっ!」
指先から、肉が焼けるような激痛が走る。
祖父の妄執が、新たな器である僕へとなだれ込んでくる。
血管の中を、砂が流れるような感覚。
「時雨、やめて、返して!」
茜の手が伸びる。
だが、その手はもう僕に触れることはできない。
因果は移った。
彼女の体は実体を取り戻し、代わりに僕の指先が、サラサラと砂になって崩れ落ちていく。
「時間を、正しい流れに戻す」
僕は砂時計を高く掲げ、地面に叩きつけた。
パリン、という硬質な音が響く。
放たれた琥珀色の砂が、竜巻となって僕を包み込む。
視界が白く塗りつぶされていく。
茜の叫び声が、水底で聞くように遠ざかる。
怖い。
寒い。
暗い。
でも、最後に見た君の姿は、ちゃんと元の色彩を取り戻していた。
「……忘れないで」
口が動いたかわからない。
喉が砂になって崩れていく。
「僕は消えるんじゃない。君の思い出の中に、溶けるだけだ」
光が弾けた。
世界は静寂に包まれた。
最終章 陽だまりの砂粒
カチリ。
ガラスが触れ合う、微かな音で目が覚めた。
茜は作業台に突っ伏していた。
顔を上げると、窓の外からは柔らかな朝の光が差し込んでいる。
雨上がりの匂い。
雀のさえずり。
いつもの、平和な朝。
「……夢?」
彼女は呆然と周囲を見渡した。
工房には何も変わった様子はない。
ただ一つ。
作業台の上に、青い砂の入った砂時計が置かれている以外は。
胸の奥に、ぽっかりと穴が開いたような感覚があった。
心臓の鼓動が、誰かを探して不規則に脈打っている。
「おはよう、茜さん」
窓の外から、近所の老人が声をかけてくる。
「今日は一人で作業かい? 精が出るねえ」
「ええ、おはようございます。……え?」
一人?
茜は首を傾げた。
私はいつも一人だっただろうか。
いいや、違う。
誰かがいたはずだ。
口数が少なくて、嘘をつくのが下手で、いつも私のことを心配そうに見つめていた、誰かが。
「……名前が、出てこない」
茜は震える手で、青い砂時計を手に取った。
不思議な温もりがある。
まるで、誰かの体温を閉じ込めたような。
彼女は何気なく、その砂時計をひっくり返した。
サラサラと、美しい青い砂が落ちる。
その、瞬間。
『――君の思い出の中で、ずっと生き続けるから』
優しい声が、脳裏ではなく、心臓の奥で響いた。
同時に、視界が一変する。
窓から差し込む陽の光。
棚に並んだガラス細工の輝き。
舞い上がる埃のひとつひとつ。
その全てに、『彼』がいた。
彼が命を賭して守った「世界そのもの」が、茜を優しく抱きしめていた。
涙が、一雫、砂時計のガラスに落ちて弾ける。
「……時雨」
名前を呼んだ瞬間、あふれ出した記憶が色彩となって蘇る。
彼の不器用な笑顔。
コーヒーの香り。
繋いだ手の温もり。
彼は消滅したのではない。
この世界の「光」や「風」となって、今もここにいる。
「馬鹿ね……。忘れられるわけ、ないじゃない」
茜は砂時計を胸に抱きしめ、くしゃくしゃの顔で笑った。
ガラス越しに伝わる微かな振動は、確かに彼が生きた証だった。
悲しみはある。
二度と触れられない寂しさは、きっと消えない。
けれど、それ以上に大きな「愛された記憶」が、彼女の背中を支えていた。
「行こう。あなたが守ってくれた、今日を生きるために」
茜は涙を拭い、工房の重い扉を両手で押し開けた。
雨上がりの空に、七色の虹が架かっていた。