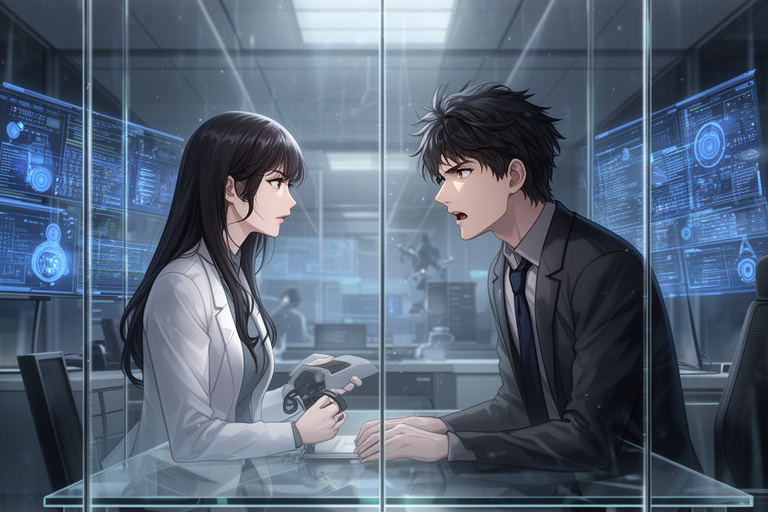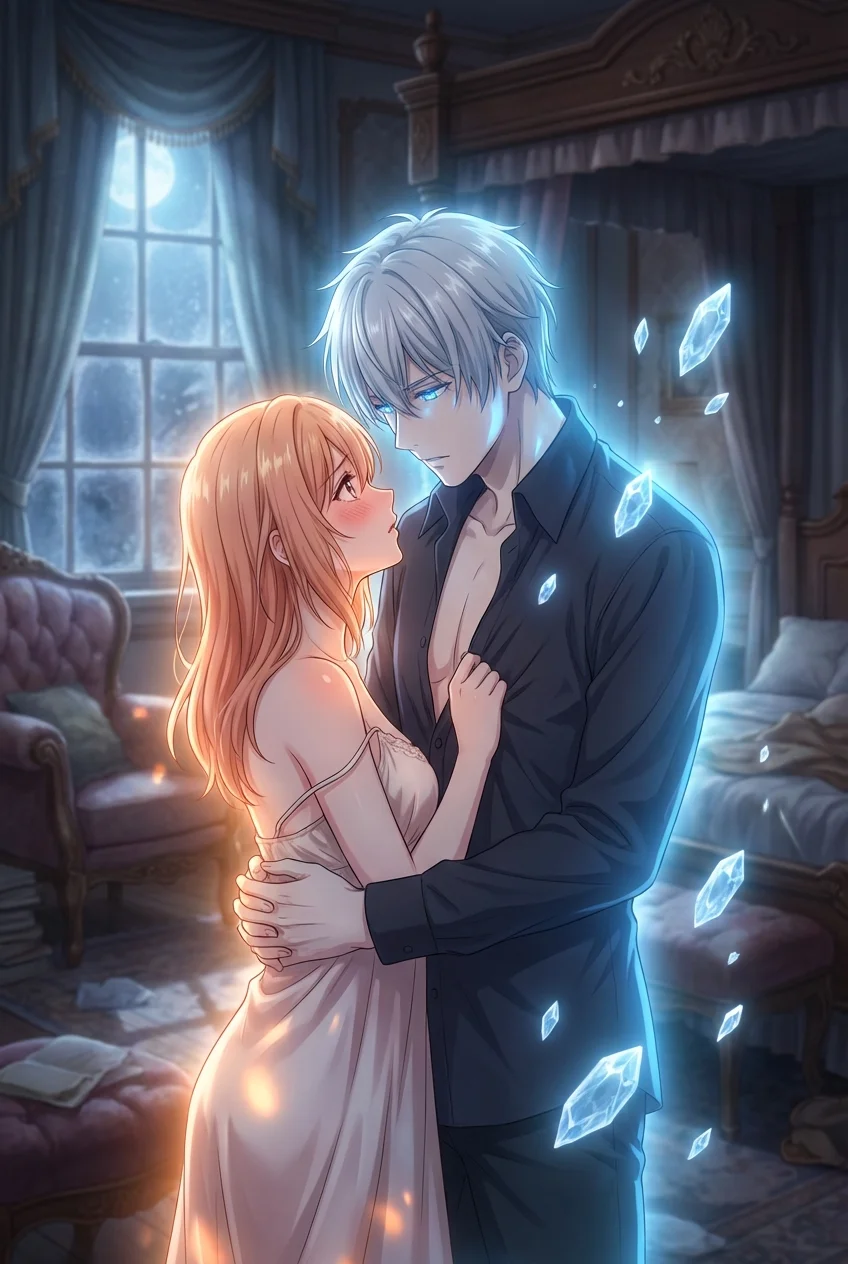第一章 禁忌の調香
雨の匂いが、地下室の冷たい空気と混ざり合う。
湿ったコンクリート、古びた洋書の埃、そして微かなカビの気配。
外界から遮断されたこの場所は、私、桐生 薫(きりゅう かおる)だけの聖域であり、牢獄だった。
背後で重い扉が軋む音がした瞬間、私の嗅覚領域(テリトリー)は、異質な分子によって蹂躙された。
振り向かずとも分かる。
雨に濡れたウール、微かな煙草の残り香、そして冷徹なベルガモットのトップノート。
「……また、来たのね」
「鍵が開いていた。招かれていると解釈したが」
神宮寺 蓮(じんぐうじ れん)。
宿敵「AURORA」の次期総帥にして、本来ならその気配を感じることすら許されぬ男。
彼が歩を進めるたび、私が調合していた繊細なフローラルの香りが、彼の圧倒的な存在感によって書き換えられていく。
「出て行って。ここにあるのは、あなたたちの望む『市場価値』のある商品じゃないわ」
「商品など求めていない」
距離が詰まる。
私の首筋に、彼の体温が近づくのを感じた。
「求めているのは、お前の肌から立ち昇る、その不協和音(ディスコード)だ」
耳元で落とされた言葉は、低く、重力のように私を縛り付ける。
私は震える手で、実験台の上の小瓶を握りしめた。
『月影の香』。
私の不安定な精神を繋ぎ止めるための、鎮静と麻痺の調合。
「近づかないで。……私の香りは、あなたを拒絶しているはずよ」
「拒絶? いいや、分析が甘いな」
蓮の手が、私の手首を掴んだ。
強く、けれど脈拍を確かめるように繊細に。
「拒絶のスパイスの奥で、甘いインドルが腐敗寸前の芳香を放っている。……お前は、混ぜ合わされることを待っている」
彼は私の手から小瓶を取り上げると、その琥珀色の液体を一滴、彼自身の指先に垂らした。
そして、その指を私の唇へと押し当てる。
「舐めろ。これが、我々の契約だ」
物理的な接触よりも先に、強烈な香りが私の脳髄を直撃した。
彼の指の温度で急激に揮発した液体が、鼻腔を突き抜け、海馬を揺さぶる。
夜来香(イエライシャン)の濃厚な甘さが、彼の持つ鋭利なシトラスと衝突し、爆発的な化学反応を起こす。
それは暴力的なまでの、感覚の支配。
「ん……っ」
私の唇が、抗うことを忘れて開いた。
舌先に触れた苦味と、鼻孔を満たす陶酔。
色彩を持たないはずの香りが、鮮烈な真紅のイメージとなって視界を埋め尽くす。
家名も、掟も、理性という名の保留剤(フィキサティブ)さえも、この圧倒的な揮発性の前では無意味だった。
ただ、彼という強烈なベースノートに、私が飲み込まれていく。
私たちは言葉を失い、ただ互いの匂いを貪るように求め合った。
第二章 嘘と真実のアンフルラージュ
古びたソファが、重みに耐えかねて音を立てる。
嵐のような時間が過ぎ去り、部屋には濃密な沈黙だけが澱んでいた。
静寂の中で、私はある違和感に鼻を鳴らした。
先ほどまでの陶酔が薄れ、冷静な分析官としての嗅覚が戻ってくる。
蓮のシャツから漂うサンダルウッドの落ち着いた香り。
その層(レイヤー)の奥底に潜む、異質なノイズ。
鼻の奥がツンと痛むような、冷たい金属と灰の匂い。
――嘘の匂いだ。
脳裏に、幼い日の光景がフラッシュバックする。
暖炉の前で父が燃やしていた手紙。
炎に巻かれる紙片から立ち昇る、秘密を葬り去る時の、あの焦げ臭い罪悪感の記憶。
彼が、何かを隠している。
「……何を探りに来たの」
私は身を起こし、乱れたブラウスの襟を合わせた。
「AURORAの重役たちが、KIRYUの『原香』を狙っているのは知っているわ」
蓮は無言のまま、懐から一束の古文書を取り出し、テーブルの上に放った。
「探りに来たんじゃない。答え合わせをしに来たんだ」
「これは……?」
「ウチの金庫に眠っていた『下半分』だ。お前のところにある『上半分』と突き合わせてみろ」
私は息を呑み、棚の奥から厳重に保管していた封筒を取り出した。
黄ばんだ羊皮紙。黒塗りで隠された処方箋。
二つの紙片を並べる。
断絶していたインクの線が繋がり、一つの複雑怪奇な分子構造式が浮かび上がった。
言葉による説明など不要だった。
その構造式を見た瞬間、調香師としての私の直感が警鐘を鳴らし、同時に歓喜の声を上げたのだ。
「そんな……。これ、単なる香水のレシピじゃないわ」
「ああ。揮発温度の異なる二種類の液体を、時間差で共鳴させる構造だ」
蓮が指先でその図面をなぞる。
「KIRYUの処方は、36度以下の低温で香りが閉じる『封印』の構造。対してAURORAの処方は、38度以上の高温で初めて分子が崩壊し、香りを放つ『解放』の構造」
点と線が繋がった。
なぜ、二つの家が対立し、決して交わってはならなかったのか。
「二つの香料をただ混ぜるだけじゃ、互いの成分を打ち消し合って『無臭』になる……」
私は震える声で呟いた。
「でも、もし……異なる体温を持つ二人が、至近距離で触れ合い、互いの体温を媒介(ブリッジ)にしてこの香料を温めたら?」
「低温の封印が解かれる瞬間に、高温の解放が重なる」
蓮の瞳が、暗い熱を帯びて私を射抜いた。
金属と灰の匂い――あれは嘘の匂いではなかった。
彼が抱えてきた、孤独な使命の焦げ付くような残り香だったのだ。
彼は、この仮説を立証するために、家を、名誉を、すべてを灰にする覚悟でここに来た。
「薫。俺たちの体温の差は、絶妙な不均衡(アンバランス)だ。俺とお前でなければ、この香りは完成しない」
「完成させて、どうするの? これは、世界を狂わせる毒かもしれないのに」
「毒か薬か、嗅いでみるまでは分からない。……だが」
彼は立ち上がり、私の頬に手を添えた。
その掌は熱く、私の冷えた肌を灼くようだ。
「俺たちはもう、この香りなしでは呼吸すらできない体になっている。そうだろ?」
反論できなかった。
彼の言う通り、私の肺はすでに、彼という酸素を求めて悲鳴を上げていたからだ。
第三章 融合する魂、解放される香り
実験室の空調を切った。
空気の流れを止め、湿度と温度を私たちの体温だけで支配するために。
ビーカーの中で揺れるのは、二つの家が数百年守り抜いてきた秘薬の混合液。
色は無色透明。香りはない。
現段階では、ただの水と同じだ。
「いくぞ」
蓮の合図で、私たちはその液体を互いの脈打つ場所――手首、首筋、そして心臓の上へと塗り広げた。
ひやりとした感触。
直後、肌の上で何かが弾けるような微細な感覚があった。
「……来て」
私は彼を招き入れる。
彼の体温が私を覆い、私の体温が彼を受け入れる。
その接触面で、奇跡的な熱交換が始まった。
私の体温(36.2度)が、ベースノートの重い鎖を解く。
蓮の体温(37.5度)が、トップノートの鋭い分子を空中に放つ。
「あっ……!」
声が漏れたのは、快楽のためだけではない。
視界が、黄金色に染まったのだ。
「見えるか、薫……!」
「ええ……色が、音が……!」
嗅覚が極限まで研ぎ澄まされ、五感の境界が崩壊する。
部屋中に満ちたのは、ただの「いい匂い」ではなかった。
それは、記憶の奔流。
雨上がりのアスファルト、古い図書館の静寂、初恋の切なさ、母の腕の中の安らぎ、そして命が芽吹く瞬間の爆発的なエネルギー。
相反するはずの要素が、完璧な調和(アコード)を奏でながら螺旋を描いて上昇していく。
彼が私を抱きしめる力が強まるたび、二人の皮膚の間のわずかな空間で香気が圧縮され、核融合のように新たな芳香を生み出した。
もはや、どこからが私で、どこからが彼なのか分からない。
魂の輪郭が溶け出し、一つの巨大な香りの粒子となって大気中に拡散していく。
「これが……『原香』……」
それは人を狂わせる毒ではなかった。
すべての孤独を埋め、欠けた魂を補完する、完全なる救済の香り。
絶頂の瞬間、私たちは白光する香りの渦の中で、確かに一つの生命体へと進化した。
終章 新たなる誓い
数ヶ月後、世界はある「現象」に包まれていた。
ニューヨークのタイムズスクエア、ロンドンの地下鉄、東京のスクランブル交差点。
喧騒と殺伐が支配していた場所に、ふと、柔らかな風が吹き抜ける。
その風に含まれた極微量の粒子を吸い込んだ瞬間、人々は足を止め、争っていた手を下ろした。
誰かが涙を流し、誰かが隣人の肩を抱く。
言葉による説得も、武力による制圧もなし得なかった静寂。
KIRYUとAURORAが合併し、世に送り出した新作『Union(ユニオン)』。
その香水は、人々の脳の扁桃体に直接作用し、攻撃衝動を鎮静化させ、共感能力をブーストさせる「機能性香水」として、歴史を塗り替えつつあった。
だが、市場に出回っているそれは、あくまで希釈された複製品(レプリカ)に過ぎない。
「……何を考えている?」
オフィスのバルコニーで風に当たっていると、背後から蓮が腕を回してきた。
彼の体温に触れた瞬間、私たち二人の間だけで、本物の『Union』が揮発する。
市場品には決して真似できない、愛し合う二人の体温差のみが生み出せる、オリジナル・ノート。
「世界が変わったわ。……少しだけ、怖いくらいに」
「世界が変わったんじゃない。世界が、本来の呼吸を取り戻しただけだ」
蓮は私の髪に鼻を埋め、深く息を吸い込んだ。
「それに、俺たちの仕事は終わっていない。この香りは、俺たちが離れれば消えてしまう。世界を繋ぎ止めておくには、俺たちは一生、離れることが許されない」
それは、かつての「掟」よりも遥かに重く、そして甘美な拘束。
「望むところよ。調香師として、最高傑作の管理義務を果たさなきゃいけないもの」
私は振り返り、彼の唇に触れた。
そのキスは、契約の更新。
ふわりと、バルコニーから風が舞い上がる。
私たちの肌から生まれた目に見えない粒子が、金色の光となって空へと溶けていく。
その香りは、遠く海を越え、誰かの孤独な夜に届くことだろう。
月影の下、私たちは互いの体温を確かめ合いながら、終わりのない調香を続けていく。
『』