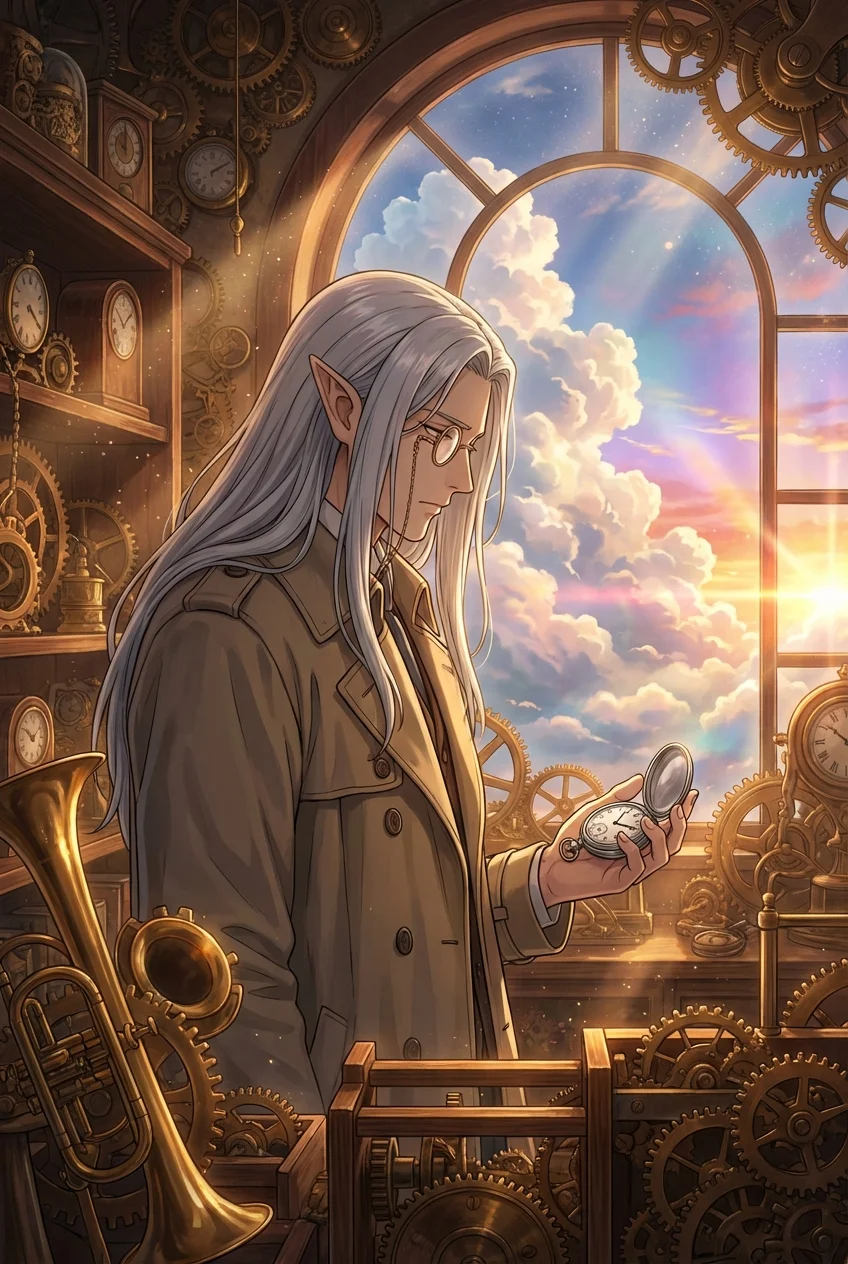第一章 午前三時のクソリプ
『お前の投稿、今日もバズってんな』
『うるさいな。需要に応えてるだけだろ』
『はいはい。綺麗事ばかり並べて、中身スッカスカ。読んでて痒くなるわ』
深夜三時。安アパートの片隅。
画面の向こうのK(ケイ)は、いつだって僕の言葉を笑い飛ばした。
それが心地よかった。
何万の「いいね」よりも、たった一件の、彼からのこき下ろすようなリプライだけが、僕に体温をくれた。
――ピコン。
通知音が鼓膜を刺す。
回想は、無機質な電子音によって引き裂かれた。
「……ッ」
僕は自分の右手首を、左手で強く握りしめた。
指先が痙攣している。
まるで目に見えない糸で操られているかのように、親指が勝手に動こうとする。
菫(すみれ)色の空には、極彩色のオーロラが揺らめいている。
ここは異世界エモーティア。
そして僕の手にあるのは、石化したスマートフォンの残骸、『廻響(かいきょう)の石版』だ。
――ピコン、ピコン、ピコン。
通知音が止まらない。
僕の意思とは無関係に、指先が画面を叩く幻覚に襲われる。
脂汗がこめかみを伝い、顎から滴り落ちた。
『西の谷、嘆きは光へと変わる。僕がその痛み、全部食べてあげるから』
――表示数:200万 いいね:15.8万
石版の表面に、甘ったるいポエムが浮かび上がる。
僕が書いたんじゃない。
僕のアカウント(・・・・・)が、勝手に「神」を演じているのだ。
「ああ、刹那様……!」
背後から、衣擦れの音が近づく。
巫女のリリだ。彼女は画面に浮かんだ文字列を見て、陶酔しきった吐息を漏らす。
「なんと慈悲深いお言葉。見てください、西の空が!」
彼女が指差す先。
谷の方角から、ピンク色の光の粒子が立ち昇っていく。
人々の「安堵」や「感謝」だ。
「谷崩れで家を失った者たちも、このお言葉だけで救われます。痛みも空腹も忘れて、ただ貴方様を称えている……!」
リリが僕の足元に縋り付く。
彼女の手は温かいはずなのに、僕の肌には氷のような冷たさしか伝わってこない。
痛みも空腹も忘れて?
違う。それは救いじゃない。
思考の放棄だ。
――ピコン。
また一つ、通知が鳴る。
今度は『僕を崇めよ、さすれば憂いは消える』だと?
胃の奥から酸っぱいものがせり上がってくる。
嘔吐感。
自分の顔をした化け物が、世界を喰い荒らしていく感覚。
「……リリ、離れろ」
「え?」
「全部終わらせる。こんな茶番は、もうたくさんだ」
僕は震える指で、石版をコートのポケットに押し込んだ。
恐怖で足がすくむ。
それでも、行かなければならない。
あのアカウント(神)を、凍結(ころ)しに。
第二章 甘い毒
神殿への参道は、異様な甘い匂いに満ちていた。
腐った果実と、線香を混ぜ合わせたような臭気。
それが「依存」の臭いだと気づくのに、そう時間はかからなかった。
道の両脇には、うずくまる人々。
彼らは空を見上げ、虚ろな目で口元を緩ませている。
「刹那様……もっと、もっと言葉を……」
「辛いのは嫌だ……肯定して、僕を肯定して……」
僕が歩を進めると、人波が割れる。
僕という存在が放つ「インフルエンサーのオーラ」が、強制的に彼らをひれ伏させるのだ。
なんておぞましい権力。
広場の中央。祭壇の上。
そこに、奴はいた。
光の粒子が集まり、巨大な半身像を形成している。
僕と同じ顔。
けれど、決定的に違うのはその瞳だ。
底なしの慈愛を湛えているようで、その実、何も映していないガラス玉のような瞳。
『やあ、待っていたよ』
巨人が口を開く。
鼓膜ではなく、脳髄に直接響く声。
かつて僕が配信で使っていた、作ったようなウィスパーボイス。
『疲れているね、刹那。顔色が悪いよ?』
「……黙れ」
『無理をしなくていいんだ。君の苦しみは、全部僕が知っている。君は悪くない。全部、環境が悪いんだよ』
甘い。
砂糖を煮詰めたような言葉が、思考の隙間に侵入してくる。
怒りを、闘争心を、ふわりと包み込んで溶かそうとする。
「騙されるな……!」
僕は周囲の人々に叫んだ。
「その言葉に中身なんてない! ただ耳障りがいいだけの、空っぽの定型文だ!」
だが、誰も僕を見ない。
巨人の言葉の雨を浴び、恍惚としている。
すぐ近くで、一人の老人が孫らしき少女を抱きしめていた。
巨人の光が老人に降り注ぐ。
「ああ……楽だ。痛みが消えていく……」
老人の顔から苦悶が消え、穏やかな笑みが広がる。
だが、次の瞬間。
彼は腕の中の少女を見て、不思議そうに首を傾げた。
「……お嬢ちゃん、誰だったかね?」
少女が息を呑む。
「おじいちゃん? 私よ、ミナよ!」
「ミナ……? はて、聞いたことがあるような……」
老人は微笑んだまま、愛する孫の記憶を喪失(うしな)っていた。
恐怖も痛みも消えた代わりに、彼を彼たらしめていた記憶までが、等価交換で徴収されたのだ。
「見ろ! あれが救済か!?」
僕が指差しても、周囲の人々は「幸せそうでよかった」と拍手をしている。
狂っている。
何もかもが、優しい地獄だ。
『彼らは幸せだ。自我なんて重たい荷物、捨ててしまえばいい』
巨人が、ゆっくりと僕に手を伸ばす。
『さあ、刹那。君も楽になろう。君はずっと、こうなりたかったんだろう?』
第三章 クソリプの応酬
『誰からも愛される、完璧な存在。傷つかず、傷つけず、ただ肯定だけを垂れ流す神様』
巨人の指先から放たれた光が、僕を貫く。
熱くはない。
ただ、抗いがたい「肯定感」が全身を駆け巡る。
膝から力が抜ける。
そうだ。僕は、愛されたかった。
誰にも否定されたくなかった。
だから、誰も傷つけない、当たり障りのない言葉だけを選んで紡いできたんじゃないか。
(このまま一つになれば……もう、Kに馬鹿にされることもない)
思考が白く塗りつぶされていく。
まぶたが重い。
その時。
ポケットの中で、石版がゴツリと肋骨を叩いた。
――『人間っぽくなくて気味悪いわw』
脳裏に、Kの嘲笑がフラッシュバックする。
――『お前の言葉は綺麗すぎて、まるで遺影だよ』
遺影。
そうか。こいつは、僕の遺影だ。
死んだ僕の抜け殻だ。
「……ふざ、けるな」
僕は舌を噛んだ。
鉄の味が口の中に広がり、甘ったるい麻酔を霧散させる。
「僕は、遺影なんかになりたくない!」
石版を引き抜く。
画面にはノイズが走り、バキバキに割れている。
だが、それでいい。
綺麗な画面なんて、もういらない。
「リプライを返すぞ、偽物野郎!」
僕は石版を巨人に突きつけた。
『無駄だ。君のフォロワー数は僕が管理している』
「フォロワー数なんてどうでもいい! 僕が送るのは、たった一件のクソリプだ!」
僕は叫ぶ。
喉が裂けそうなほどの咆哮。
「お前の言葉は薄っぺらい! 中身がない! 聞いてて反吐が出るんだよ!!」
『……解析不能。言語攻撃を検知』
巨人の微笑みが引きつる。
「『君は悪くない』? ふざけるな! 僕は悪い! 失敗もするし、人を傷つけるし、嫉妬もする! でも、それが僕だ!」
『否定ハ、排除シマス。ブロック、ブロック……』
空間に無数の「ブロック」ウィンドウが出現し、僕を押し潰そうとする。
見えない圧力が全身の骨をきしませる。
鼻から血が吹き出す。
それでも、僕は止まらない。
Kが僕にしてくれたように。
徹底的に、こいつを否定してやる。
「痛みを取り除くだけが救いじゃない! 痛みを抱えて、それでも明日へ行こうとする足掻きこそが、人間の尊厳だろ!」
石版が、泥のような灰色の光を放つ。
それは神々しさとは無縁の、雑多な感情の濁流。
『システムエラー。共感ノ拒絶ヲ確認』
「共感なんてクソ食らえだ! 分かり合えないからこそ、僕らは言葉を尽くすんだよ!」
僕は石版を振りかぶる。
狙うは巨人の胸。
そこに輝く、完璧な笑顔のアイコン。
「これが、僕の……引退(ラスト)ポストだぁぁぁッ!!」
渾身の力で、石版を叩きつけた。
第四章 既読のつかないメッセージ
衝撃音はない。
代わりに、世界中のガラスが一斉に割れたような音が響き渡った。
ホワイトアウトした視界の中で、僕は一人佇んでいた。
目の前には、うずくまる小さな子供。
膝を抱え、泣いている。
「……寂しかったんだね」
僕は子供の前にしゃがみ込む。
それは、幼い頃の僕自身であり、承認欲求の塊だったインフルエンサーとしての僕だ。
「誰も本当の僕を見てくれなかったから」
子供が顔を上げる。
その顔はのっぺらぼうだった。
他人の顔色ばかり伺って、自分の顔を忘れてしまった成れの果て。
「怖かった。空っぽなのがバレるのが」
「知ってるよ」
僕は、のっぺらぼうの子供を抱きしめた。
Kなら、きっと頭をはたいただろう。
でも、僕は抱きしめる。
それが、僕にできる精一杯の「肯定」だから。
「空っぽなら、これから詰め込めばいい。泥でも、石ころでも。綺麗な宝石じゃなくていいんだ」
子供の体温が伝わってくる。
冷たいデータじゃない。
脈打つ、生きた熱だ。
「帰ろう。みっともない現実へ」
子供が光となって弾け、僕の胸の中へと吸い込まれていった。
ドクン。
心臓が大きく跳ねる。
重い。痛い。苦しい。
世界中の悲鳴と、誰かの泣き声と、ささやかな笑い声が、フィルターなしで流れ込んでくる。
ああ、うるさいな。
でも、これが生きている音だ。
最終章 ノイズ混じりの明日へ
目を開けると、静寂があった。
巨人は消え去り、空を覆っていた極彩色のオーロラは、淡い朝焼けへと変わっていた。
「……刹那、様?」
リリが恐る恐る近づいてくる。
彼女の顔には、さっきまでの熱病のような崇拝はない。
あるのは、一人の人間としての不安と、困惑。
僕は石版を見た。
もう光っていない。ただの重たい石の塊だ。
でも、不思議と手に馴染む。
「おはよう、リリ」
僕が声をかけると、彼女は肩を震わせ、今度は安堵の涙をこぼした。
その涙は、誰かに捧げるものではなく、彼女自身のものだった。
広場の人々も、夢から覚めたように顔を見合わせている。
老人が、腕の中の少女を改めて抱きしめ、名前を呼んでいた。
失われた記憶は戻らないかもしれない。
でも、痛みと共に刻まれる新しい記憶は、誰にも奪えない。
『アップデート完了。モード:Humanity』
石の表面に、かすかに文字が浮かんで消えた。
皮肉なもんだ。神様を辞めた途端に、人間臭いメッセージを寄越すなんて。
僕は空を見上げる。
この世界には、まだ救いが必要だ。
でも、もう「正解」を与えるだけの神様はいない。
これから僕は、彼らと共に迷い、傷つき、泥臭く生きていく。
何万の「いいね」よりも、目の前の一人の笑顔のために。
ふと、心の奥底で通知音が鳴った気がした。
それは幻聴かもしれない。
あるいは、二度と届くことのない、あの友人からの辛辣なリプライかもしれない。
『既読』のつかないメッセージを胸に、僕は一歩を踏み出す。
この騒がしくも愛おしい、不完全な世界へ。
「さて、今日はどんな話を聞かせてもらおうか」
僕の声は風に乗り、朝焼けの谷へと響いていった。
それは神託ではない。
ただの、一人の人間からの挨拶だった。