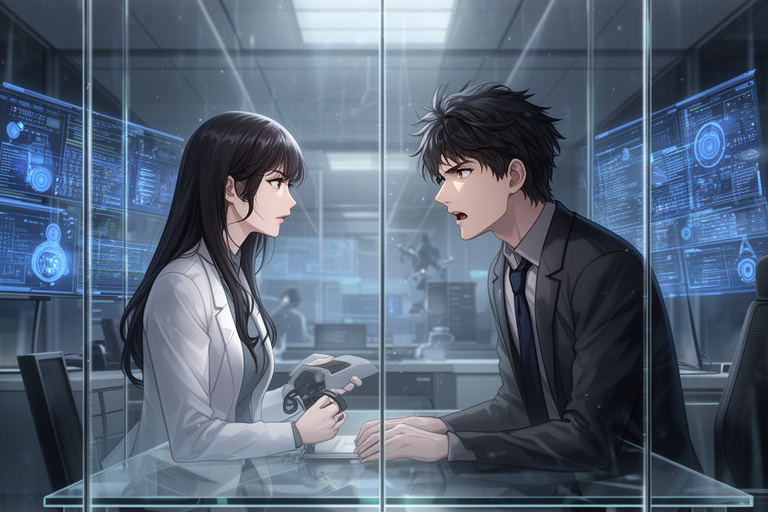第一章 偽りの聖域
シャンパングラスが触れ合う硬質な音が、鼓膜を突き刺す。
完璧に調律されたピアノの旋律。
絹擦れの音。
私、霧野藍にとって、このパーティー会場はあまりに騒々しい。
生まれつき過敏な聴覚は、愛想笑いの裏に隠された退屈や、商談の腹を探り合う心拍の乱れさえも拾ってしまう。
「藍くん、来てくれたね」
背後から響いた、深淵のようなバリトンボイス。
振り返ると、そこには私の恩師であり、建築界の帝王、神崎耀一が立っていた。
そして、その傍らに寄り添う、美しい青年。
時が、止まった。
呼吸が、できない。
「……奏?」
唇が震え、音にならない名前を紡ぐ。
かつて私の全てを焦がし、そして姿を消した初恋の相手。
彼がなぜ、ここに。
「紹介しよう。私の婚約者、奏(かなで)だ」
神崎の手が、奏の華奢な腰に回される。
その指先が食い込む様子に、私の肌までが痛みを覚えた。
所有印を押すような、冷酷で優雅な所作。
奏は、微笑んでいた。
けれどその瞳は、硝子玉のように光を弾くだけで、何も映していない。
「初めまして、霧野さん。神崎から、優秀なお弟子さんだと伺っています」
初めまして?
私の鼓動が、早鐘を打つ。
あれほど愛し合った夜を、肌を重ねた熱を、忘れたというのか。
私は耐えきれず、挨拶のふりをして彼の手を取った。
指先が触れた瞬間。
ビクリ、と奏の身体が跳ねる。
指の腹から伝わる、微細な震え。
脈動が、異常な速さで高鳴り始めたのを、私の鋭敏な触覚は見逃さない。
(覚えている……身体は、私を覚えている)
だが、彼の首元から漂う、甘く重苦しい香りが鼻孔を突いた。
首飾りとして下げられた、白磁のようなアロマストーン。
そこから放たれるのは、脳髄を痺れさせるような、人工的な「幸福」の匂い。
「……良い香りですね」
私が探りを入れると、神崎は満足げに目を細めた。
「彼のために調合した特別な香りだよ。精神を安定させ、永遠の美を保つためのね」
神崎の瞳の奥に、狂気じみた支配欲が揺らめく。
この香りが、奏の記憶を封じ込めている。
私の本能が、そう告げていた。
「少し、酔ってしまったようです」
奏がふらりとよろめく。
その拍子に、彼の熱い吐息が私の耳元を掠めた。
「……助けて」
音にはならない、唇の形だけの懇願。
私の理性の堤防に、致命的な亀裂が入った。
第二章 禁断の共鳴
神崎の邸宅の地下。
厳重にロックされたアトリエの扉を、私は恩師から盗み見たパスコードで解除した。
冷やりとした空気の中に、あの纏わりつくような甘い香りが充満している。
書斎の机の上。
一冊の古びた日記が開かれていた。
『被験体Kの記録』
日付は、奏が失踪した時期と重なる。
『記憶変容香の投与により、過去の人格の剥離に成功。恐怖と悲しみの記憶を消去し、私への絶対的な服従と、美への献身のみを植え付ける』
「……なんてことを」
吐き気がした。
神崎は、奏という人間を素材に、自分好みの「生きた建築」を造り上げようとしていたのだ。
「藍……?」
震える声が、闇の中から響く。
奏が、立っていた。
寝間着のシルクシャツが、彼の汗ばんだ肌に張り付いている。
虚ろだった瞳に、今は激しい葛藤と、熱っぽい潤みが宿っていた。
「ここに来てはいけない……先生に、怒られる……」
「奏、思い出して。私よ」
私は彼に歩み寄る。
拒絶の言葉とは裏腹に、彼から発せられる熱気は、私を求めていた。
アロマストーンの香りが、変化し始める。
甘ったるい花の香りから、もっと生々しい、麝香のような香りへ。
それは、私たちがかつて共有した、情事の記憶を呼び覚ますトリガー。
私は彼のアロマストーンを握りしめ、その唇を塞いだ。
「んっ……!」
微かな抵抗は、一瞬で溶けた。
舌が絡み合う湿った音が、静寂なアトリエに反響する。
私の聴覚は、彼の中で高まる血液の奔流を、ダムが決壊する轟音のように聞いていた。
「あ、ぁ……藍、だめ、壊れちゃう……」
「いいの。壊れてしまえばいい」
私は彼を机の上に押し倒す。
神崎の研究資料が、床に散乱する。
理性のタガが外れる音。
それはどんな建築物が崩落する音よりも、甘美で、破壊的だった。
シャツのボタンを引きちぎるように外す。
露わになった彼の肌は、上気して桜色に染まっている。
私の指が、彼の敏感な部分をなぞるたび、アロマストーンの香りが毒々しいほどに濃くなる。
それは背徳の香り。
罪の味。
「先生の……ものなのに……」
「違う。あなたは私のもの」
私は彼の耳元で囁き、首筋に深く、所有の証を刻み込んだ。
「ああっ! ……深い、そこ……!」
彼の背中が弓なりに反る。
私の五感は、今や彼という存在そのものを飲み込もうとしていた。
肌のきめ、汗の味、うわごとのような喘ぎ声。
その全てが情報として私の中に流れ込み、私の脳を焼き尽くす。
もはや、止まらない。
私たちは、互いを食らい合う獣のように、深く、激しく、混ざり合っていった。
第三章 崩落する伽藍
「素晴らしい……!」
狂喜の声が、頭上から降ってきた。
アトリエの吹き抜けの回廊に、神崎が立っている。
私たちを見下ろすその目は、怒りではなく、恍惚に満ちていた。
「これだ! 私が求めていたのは、この『背徳』という名の最後のピースだ!」
神崎は両手を広げ、叫ぶ。
「純白のキャンバスは汚されてこそ完成する! さあ、もっと堕ちたまえ! 君たちの罪深さが、私の建築を神の領域へと昇華させるのだ!」
彼は私たちさえも、演出の一部として利用していたのだ。
その傲慢さが、私の中で眠っていた「何か」を目覚めさせた。
(ふざけるな……)
奏の身体が、恐怖で硬直する。
彼の中で、神崎の植え付けた支配のプログラムが作動しようとしている。
「いやだ……藍、助けて……怖い……!」
奏が頭を抱え、錯乱し始める。
アロマストーンが、どす黒く変色していく。
(許さない。私の奏を、これ以上お前の玩具にはさせない)
私は、震える奏を抱きしめたまま、意識を極限まで集中させた。
私の特異な感覚。
それは、物質の構造的な弱点を見抜く力。
そして今、私の前にあるのは、神崎が築き上げた「精神の檻」という建築物だ。
奏との結合部分から、彼の魂の奥底へ潜る。
熱い粘膜の接触を通じて、彼の精神回路に干渉する。
そこには、神崎の言葉、恐怖、洗脳が、歪な柱となって彼を支えていた。
(ここが、核(コア)ね)
私は、奏の中で最も感じやすい場所を、執拗に、慈悲なく刺激した。
快楽という名の爆薬で、支配の柱を内側から破壊する。
「あ、ああっ! 藍、おかしくなる、頭が、溶けるぅぅッ!」
「溶けて、奏。全部忘れさせてあげる」
激しい律動と共に、私は彼の精神の深淵へ、快楽の杭を打ち込む。
波が、来る。
巨大なうねりが、私たちを飲み込む。
「い、逝く……ッ! 先生、いや、藍、あいぃぃッ!!」
奏の絶叫と共に、アロマストーンが砕け散った。
パリーン、という清冽な音が、神崎の笑い声を切り裂く。
同時に、アトリエ全体が激しく振動した。
神崎の支配の象徴であるこの空間が、主を失ったかのように軋みを上げる。
「な、何だ!? 私の完璧な設計が……!」
神崎が狼狽する。
奏の瞳から、洗脳の霧が晴れていく。
しかし、その後に残ったのは、かつての清らかな瞳ではなかった。
欲望と、背徳と、底なしの依存を湛えた、昏い瞳。
彼は私にしがみつき、涙を流しながら、狂ったように微笑んだ。
「藍……もっと……もっと頂戴……」
神崎の築いた城は、崩れ去った。
だが、私たちは瓦礫の中から這い上がることはなかった。
最終章 永遠の螺旋
誰も知らない、海岸沿いの廃屋。
波の音だけが、私たちの世界を満たしている。
神崎は失脚した。
自身の最高傑作が、最も醜悪なスキャンダルによって崩壊したことで、彼の権威は地に落ちたのだ。
だが、そんなことはどうでもいい。
「藍……」
奏が、シーツの中で私を呼ぶ。
あの日以来、彼の記憶は完全には戻らなかった。
いや、正確には、彼は「壊れた」ままだ。
善悪の区別も、時間の感覚も曖昧になり、ただひたすらに、私からの快楽と愛だけを求める存在へと変貌した。
「ここ……寂しいよ。早く埋めて」
彼が自らの肌をはだけ、欲情に濡れた瞳で私を見上げる。
その姿は、かつてのどの芸術品よりも淫らで、美しかった。
私は彼の上に覆いかぶさる。
神崎の支配からは解放された。
けれど、私たちはもう二度と、日の当たる場所には戻れない。
社会的な死。
道徳からの逸脱。
それでも、この肌の温もりだけが真実だ。
「愛しているわ、奏」
「うん……僕も、藍の中に入りたい……溶けてなくなりたい……」
彼の首筋に噛みつくと、甘い甘い蜜の味がした。
アロマストーンなどもういらない。
私たち自身が、互いを蝕み、満たし合う毒なのだから。
波音が激しさを増す。
それに呼応するように、私たちの吐息も熱を帯びていく。
理性など、とうに焼き切れた。
この終わりのない情欲の螺旋こそが、私たちにとっての唯一の救済。
私は彼を抱く。
何度でも、何度でも。
世界が果てるその瞬間まで、この背徳の陶酔に溺れ続けるために。