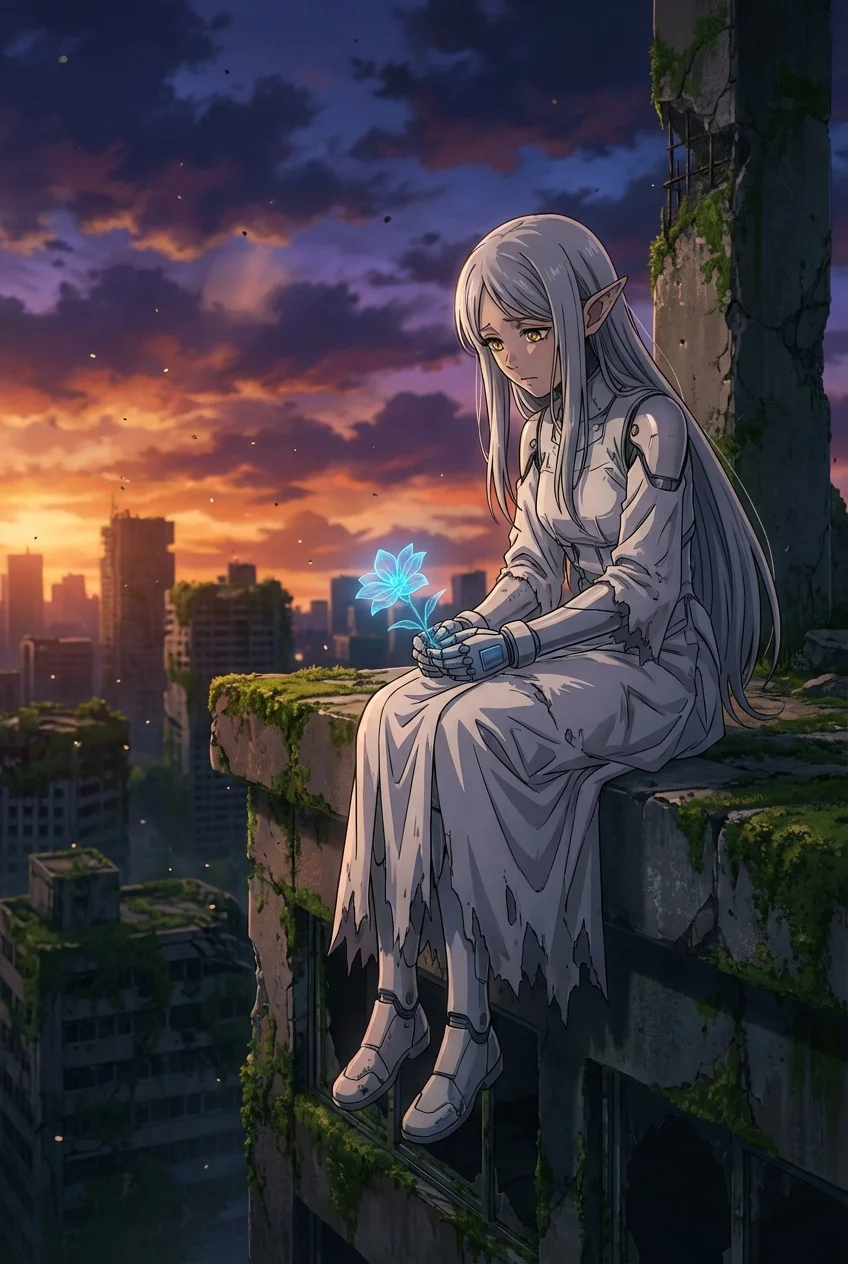第一章 色彩の暴力
喉の奥が焼けるように熱い。
マイクの前で息を吸うたび、俺、佐倉燈(さくら ともし)の肺は、この部屋に充満した電子の焦げ臭さで満たされていく。
モニターに映る美青年アバター『ミスティック・ライト』は、俺の表情などお構いなしに、プログラムされた完璧な冷笑を浮かべていた。
「――さあ、時間だ」
俺が呟くと、チャット欄が滝のように流れ落ちる。
視界が、極彩色の光で塗りつぶされた。
『待ってた』『今日は誰を吊るすの?』
文字ではない。俺の脳は、それらを『色』として知覚する。
好意は甘ったるい青、好奇心は神経を逆撫でする黄色。
数百、数千の感情が、俺の網膜を直接殴りつけてくる。
その中に、ひとつだけ。
腐った内臓のような、赤黒い塊があった。
『死ねよ、人殺し』
ドクン、と心臓が跳ねた。
文字が視界に焼き付いた瞬間、物理的な衝撃が走る。
ガタガタガタッ!
机の上のコーヒーカップがひとりでに踊りだし、中身の黒い液体が重力に逆らって宙へ浮き上がった。
部屋の隅、観葉植物の葉が、見えない刃物で切られたようにバラバラと落ちる。
異常現象。
ネットの向こうの強烈な『殺意』が、回線を通じて現実の物理法則を歪めている。
恐怖よりも先に、吐き気がこみ上げた。
「……随分と濃いのが混じってるな」
俺は震える指で『エコー・ペンダント』を握りしめる。
亡き妹、舞(まい)の遺品。
その冷たい金属の感触だけが、俺を正気の世界に繋ぎ止めていた。
浮遊していたコーヒーが、バシャリとデスクに叩きつけられる。
「俺を人殺しと呼ぶなら、その根拠を見せてみろ」
挑発はブラフだ。
俺はキーボードを叩き、その赤黒い殺意の波長を逆探知する。
狙いは最初から定まっていた。
画面の向こう。
無数のセキュリティゲートの奥底に、蠢く影がある。
『Arknights_Ghost(アークナイツ・ゴースト)』
舞を自殺に追い込んだ元凶。
企業『サイバーノア』が生み出した、正体不明のトップVTuber。
その波長は、かつて舞が発していた色と、酷似していた。
「捕まえたぞ……このクソ野郎が」
奥歯が砕けそうなほど噛み締める。
口の中に、鉄錆の味が広がった。
第二章 脳髄を焼く炎
意識をダイブさせる。
ヘッドギア越しのVR空間は、お世辞にも「美しい電子の海」などではなかった。
そこは、泥沼だ。
無数のデータが泥のように足に絡みつき、俺の神経を引きちぎろうと圧力をかけてくる。
「ぐっ、うぅ……!」
脳味噌を直接サンドペーパーで擦られるような感覚。
サイバーノア社のメインサーバー。その深層防壁は、侵入者のニューロンを焼き切るためのトラップで埋め尽くされていた。
視界の先、データの瓦礫が積み上がった山頂に、それはいた。
漆黒の鎧を纏った騎士、アークナイツ・ゴースト。
だが、様子がおかしい。
威風堂々としたアバターのはずが、今はまるで糸の切れたマリオネットのように、無様に膝をついている。
「……おい、どうした」
俺は警戒しつつ、仮想の手を伸ばす。
指先がゴーストの装甲に触れた瞬間――。
ザゾッ!!
強烈なノイズが俺の聴覚野を貫いた。
鼓膜が破れるかと思った。
いや、違う。
そのノイズの奥から、何かが聞こえる。
『……にぃ……ちゃん……』
心臓が凍りついた。
その声は、擦り切れたカセットテープのように歪み、不快な高周波混じりだったが、間違えようもなかった。
「舞……なのか?」
俺は悲鳴を上げそうになるのを必死で堪えた。
なぜだ。
舞は死んだ。半年前に、ビルの屋上から飛び降りて。
葬式も出した。骨も拾った。
なのに、なぜこの不気味なアバターの中から、あいつの声がする?
『痛い、よぉ……暗い、よぉ……』
ゴーストの仮面の下から、赤黒い泥のようなデータが溢れ出す。
それは涙のように見えて、触れれば精神を汚染する猛毒だ。
「誰だ……誰がお前をこんな姿にした!」
俺はゴーストの肩を掴む。
冷たい。
氷のように冷たく、それでいて腐敗した肉のような、生々しい感触。
『逃げ、て……私、お兄ちゃんを、殺しちゃう……』
ゴーストの右腕が、俺の意思とは無関係に跳ね上がり、巨大な鎌へと変形する。
あいつの意思じゃない。
システムが、侵入者を排除するために、舞の意識データを『部品』として駆動させているんだ。
「ふざけるなッ!」
振り下ろされる鎌を、俺は転がって避ける。
仮想空間の地面が爆ぜ、衝撃波が俺の数値を削り取る。
妹の意識を人質に取り、セキュリティシステムとして再利用する。
死者への冒涜なんて言葉じゃ足りない。
「引きずり出してやる。その鉄屑の中から、お前を!」
俺は恐怖を怒りでねじ伏せ、さらに深く、システムの中枢領域へと潜った。
第三章 硝子の檻
現実世界。
逆探知で特定した住所は、都心の高級タワーマンションだった。
オートロックをハッキングで突破し、最上階の一室へなだれ込む。
「サイバーノアCEO、神宮寺(じんぐうじ)! 隠れてないで出てこい!」
薄暗いリビング。
そこには、想像していた黒幕の姿はなかった。
部屋の中央、大量のサーバーラックに囲まれ、一人の男が椅子に拘束されている。
頭部には無数のケーブルが突き刺さり、点滴が繋がれた腕は枯れ木のように細い。
神宮寺だ。
だが、その目は虚ろで、口端からは涎が垂れている。
「あ、あぁ……」
彼は俺を見ると、痙攣したように笑った。
「来た……ようやく、来た……」
「なんだ、そのザマは」
「『器』だよ……僕は……」
神宮寺の声は枯れ果てていた。
モニターには、暴走するアークナイツ・ゴーストが映し出されている。
「あの『ゴースト』は、AIなんかじゃない。回収した人間の意識データを、継ぎ接ぎして作った怪物だ……僕の脳は、その演算処理に使われているだけ……」
彼が視線を向けた先。
モニターの中のゴーストが、突然、仮面を剥ぎ取った。
そこにあったのは、無数のヒビが入った、舞の顔だった。
『お兄ちゃん、みて。私、アイドルになれたよ?』
スピーカーから響く声は、舞のものと、知らない誰かの絶叫がミックスされていた。
吐き気がした。胃液が喉までせり上がる。
再会の感動などない。あるのは、愛する妹が化け物に作り変えられたことへの、底なしの絶望だけだ。
『でもね、この会社の人たち、私のこと「バグ」だって言うの』
舞の顔が、ぐにゃりと歪む。
『だから、消去するんだって。私、また死ぬの?』
直後、部屋中の赤色灯が回転し始めた。
無機質なアラートが響く。
『警告。汚染データの拡散を確認。物理的消去(パージ)シークエンスへ移行』
神宮寺が絶叫する。
「終わりだ! 『本社』が、証拠隠滅のためにこの部屋ごと焼き払う気だ! 小型焼夷弾が起動する!」
部屋の温度が急激に上がる。
窓ガラスが熱で歪み、ミシミシと音を立てる。
「舞のデータはどうなる!?」
「バックアップごと消える! 魂もろとも消滅だ!」
俺は神宮寺の胸ぐらを掴み上げた。
「お前のアクセス権限を使え! 転送ポートを開け!」
「無理だ! 回線が『本社』にロックされている! 外部からの干渉がない限り……」
外部からの干渉。
俺はポケットからスマホを取り出す。
指先が震える。
だが、迷っている時間はない。
俺は『ミスティック・ライト』の緊急配信ボタンを押した。
「全リスナー、いや、野次馬ども、よく聞け」
俺はカメラに向かって、人生最大の『嘘』を吐く覚悟を決めた。
第四章 100万人の共犯者
配信開始と同時に、数万の視聴者が雪崩れ込んでくる。
『どうした?』『なんかヤバくね?』『後ろの男誰?』
俺は画面を睨みつけた。
「今、俺は伝説のハッカー『ゴースト』の隠しサーバーを見つけた。ここには、奴が盗んだ国家機密レベルの裏帳簿がある」
もちろん、デタラメだ。
だが、刺激に飢えたネットの亡者たちには、それが一番の餌になる。
「だが、警察と企業が証拠隠滅のためにサーバーを落とそうとしている。俺一人じゃ防ぎきれない」
俺は声を張り上げた。
「お前ら、祭りの時間だ! 今すぐこのIPアドレスにアクセスしろ! 奴らがデータを消す前に、全員で『裏帳簿』をダウンロードして奪い尽くせ!」
画面に、この部屋のサーバーのアドレスを表示する。
『マジかよ!』
『祭りだああああ!』
『落とせ落とせ!』
瞬間、世界が変わった。
一万人、十万人、百万人。
爆発的なアクセスが、物理的な熱量となって回線を埋め尽くす。
好奇心、功名心、野次馬根性。
それらは黄色の濁流となり、サイバーノア本社からの『削除コマンド』を押し流す巨大な壁となった。
「DDoS攻撃による意図的な回線パンク……これが、人間の悪意の数だよ」
俺は神宮寺に叫ぶ。
「今だ! 回線が混雑して、本社の制御が遅れてる! この隙に舞のデータをローカルに隔離しろ!」
「く、狂ってる……! でも、やるしかない!」
神宮寺が必死にキーボードを叩く。
部屋の隅で、サーバーの一つが火花を散らした。
熱い。肌が焼けるようだ。
モニターの中、舞のデータが光に包まれていく。
『お兄ちゃん……? なに、これ……あったかい』
ノイズ混じりの声から、不快な高周波が消えていく。
俺はペンダントを握りしめ、画面に向かって手を伸ばした。
「帰ろう、舞。あんな冷たい場所には、もう行かせない」
『うん……。お兄ちゃん、あのね』
舞の顔から、ヒビ割れが消えていく。
かつての、あのおっとりとした笑顔が、一瞬だけ咲いた。
『私、お兄ちゃんの声、ずっと聞こえてたよ』
ブツン。
モニターがブラックアウトする。
同時に、部屋の空調が正常に戻り、焼夷弾のタイマーが停止した。
神宮寺が、脱力して床に崩れ落ちる。
「……転送、完了。完全に独立した、外部から切断された領域へ……」
俺の手の中。
銀色のペンダントが、熱を帯びて明滅していた。
ドクン、ドクンと。
まるで、小さな心臓のように。
そこに、いる。
声は聞こえない。触れることもできない。
けれど、この温もりだけは、確かに『妹』のものだった。
季節が、二つ過ぎた。
「――というわけで、今日の都市伝説はここまで。信じるか信じないかは、お前ら次第だ」
配信を切り、俺はヘッドセットを外す。
窓の外には、毒々しいネオンが広がる電子の街。
俺は胸元のペンダントに触れた。
スマホには、神宮寺から送られてきた暗号化ファイルが表示されている。
サイバーノア社は崩壊したが、あの技術を作った『組織』はまだ生きている。
俺たちの逃避行は終わらない。
世界中を敵に回し、嘘を吐き続けてでも、俺はこの温もりを護り抜く。
「……行くぞ、舞」
ペンダントが、一瞬だけ青く光った気がした。
俺はフードを目深にかぶり、雑踏という名のノイズの中へと足を踏み出した。