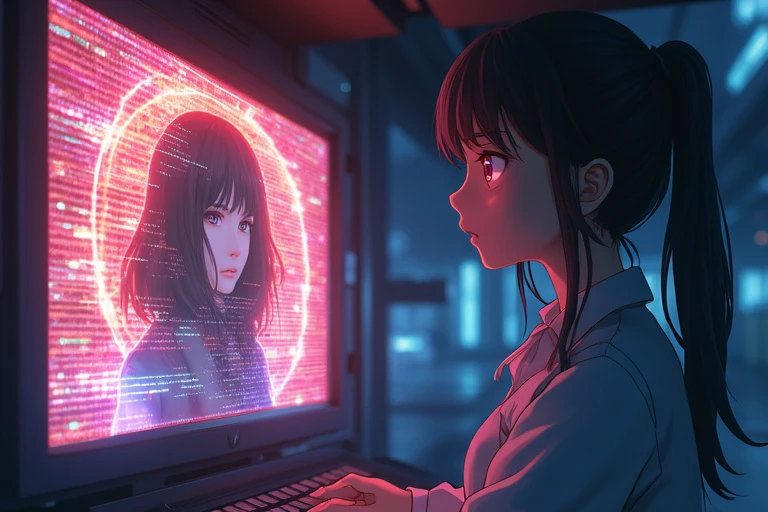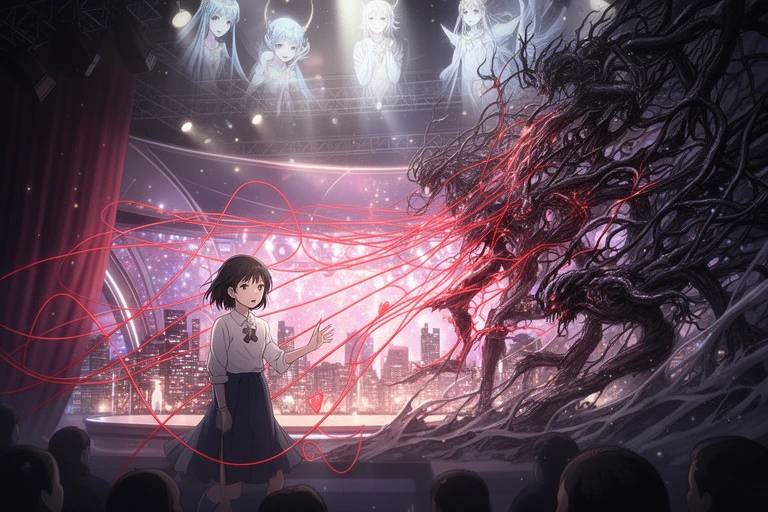第一章 廃棄された鼻
「ケイン、君の鼻はもう古いんだよ」
IDカードが床に落ちる乾いた音が、真っ白なオフィスに響いた。
「AIの調香は完璧だ。君のように『この香りは悲しい』などという主観的なノイズは必要ない」
目の前の男、アロマ・コープの最高責任者・バーンズが笑う。
彼からは、最高級の『幸福香(ハピネス・ミスト)』が漂っていた。
だが、俺にはわかる。
その甘いバニラの下に、腐った肉のような脂臭さが隠れていることが。
「……あんた、内臓が腐ってるぞ」
「は?」
「その香水でも隠しきれてない。死臭がする」
瞬間、警備ドローンが俺の腕を掴んだ。
暴力的な金属音。
「つまみ出せ! この狂人を下層(スラム)へ捨てろ!」
エレベーターホールへ引きずられながら、俺は大きく息を吸い込んだ。
消毒液と、プラスチックと、欺瞞の匂い。
俺の特異体質――『超嗅覚』。
1ppmの化学物質さえ嗅ぎ分けるこの才能は、効率化されたこの都市では、ただの欠陥品(バグ)だった。
ダストシュートが開く。
落下する風の中で、俺は逆に安堵していた。
ここには、嘘の匂いがない。
第二章 腐敗と発酵
下層(スラム)は、強烈な悪臭に満ちていた。
下水、錆びた鉄、安酒、そして排気ガス。
通常の人間なら鼻が麻痺するだろう。
だが、俺にとっては情報の宝庫だった。
「おい、兄ちゃん。いい匂いがするな」
路地裏で声をかけてきたのは、油汚れに塗れた少女だった。
右腕が剥き出しの義手。
「俺は何もつけてない」
「違うよ。あんた自身から、なんか……落ち着く匂いがする」
彼女は俺のシャツに鼻を近づけ、深く息を吸った。
「……石鹸と、古い紙の匂いだ」
俺はハッとした。
この街の人間は、合成されたフェロモン香水に脳を焼かれている。
『落ち着く』という感情さえ、薬品で強制的に引き出されるものだ。
だが、この少女は違った。
「名前は?」
「リコ。ジャンク屋やってる」
「リコ、俺に場所を貸してくれ。あと、ゴミが欲しい」
「はあ? ゴミ?」
俺は瓦礫の山を指さした。
アロマ・コープのAI調香師たちは知らない。
『完璧な香り』は、計算式からは生まれないことを。
必要なのは、時間だ。
そして、バクテリアだ。
俺は、カビの生えたパンの耳と、雨水を含んだ苔、そして錆びたパイプの欠片を集めた。
「兄ちゃん、それ腐ってるよ」
「違う。発酵(いき)てるんだ」
俺が作るのは、脳をハックするドラッグじゃない。
記憶を呼び覚ます、ただの『匂い』だ。
第三章 記憶の密売
一ヶ月後。
リコの店には長蛇の列ができていた。
彼らが求めているのは、小さなガラス瓶に入った茶色い液体。
商品名は『ノスタルジア』。
「……ああ、これは」
疲れ切った工場労働者の男が、瓶の蓋を開けた瞬間、涙を流した。
「雨の匂いだ。子供の頃、トタン屋根の下で嗅いだ……本物の雨の匂いがする」
隣の娼婦が、別の小瓶を手に取る。
「こっちは、焼けたパンと、朝日の匂い……」
アロマ・コープの香水は、脳内麻薬を分泌させて強制的に快楽を与える。
だが、俺の香水は違う。
嗅覚中枢をダイレクトに刺激し、かつて人間が持っていた『原風景』をフラッシュバックさせる。
副作用も、中毒性もない。
あるのは、圧倒的なカタルシスだけ。
「兄ちゃん、すごいよ! アロマ・コープの売上が激減してるってニュースでやってた!」
リコが端末を見せてくる。
画面の中では、バーンズが青筋を立てて怒鳴っていた。
『違法な向精神薬が出回っている! 直ちに排除せよ!』
俺は、蒸留器のバルブを閉めながら笑った。
「薬じゃない。ただの、ドブ川の水と雑草の絞り汁だ」
AIには再現できない。
なぜなら、彼らのデータセットに『不完全な美しさ』は存在しないからだ。
第四章 換気口の決戦
襲撃は深夜だった。
「見つけたぞ、ドブネズミ!」
店のドアが吹き飛び、武装したドローン部隊がなだれ込んでくる。
リコが義手のショットガンで応戦するが、数が違いすぎる。
「ケイン! 逃げて!」
「いや、逃げない」
俺は、最後の傑作が入ったタンクを抱えていた。
「リコ、都市のメイン送風機(ファン)はどこだ?」
「え? 中央広場の地下だけど……まさか」
「案内しろ。バーンズに、最高の香水をプレゼントしてやる」
瓦礫の山を駆け抜ける。
背後で爆発音。
俺たちは地下ダクトを這いずり回り、都市の空調を管理する巨大なファンルームに辿り着いた。
そこには、バーンズ本人が待ち構えていた。
「貴様か。私の帝国を汚す菌類は」
バーンズは防毒マスクをつけていた。
周りの部下たちも、完全防備だ。
「お前のその汚い液体を、ここでばら撒くつもりか? 無駄だ。我々のフィルターは99.9%の不純物をカットする」
俺はタンクの栓に手をかけた。
「バーンズ、あんたは大きな勘違いをしている」
「何だと?」
「俺の香水は、不純物じゃない。分子サイズが、あんたの規格より遥かに小さいんだよ」
俺はタンクを、吸気口へ放り投げた。
巨大なファンがタンクを粉砕する。
液体が霧となり、都市全域へのパイプラインに乗った。
「馬鹿め! 毒ガスなら警報が鳴る!」
警報は鳴らなかった。
代わりに、バーンズの部下たちが、次々と銃を下ろした。
「……なんだ、これ」
防毒マスク越しでも、その匂いは届く。
それは、母親の胸の匂い。
干した布団の匂い。
初めて恋人と手を繋いだ日の、汗ばんだ掌の匂い。
「やめろ! 撃て! 私の命令が聞けないのか!」
バーンズが叫ぶ。
だが、誰も動かない。
部下の一人が、マスクを脱ぎ捨てた。
「……社長。もう、いいでしょう」
「何?」
「俺たち、疲れました。こんな偽物の幸せは、もういらない」
第五章 呼吸する世界
都市は静寂に包まれていた。
暴動は起きなかった。
ただ、人々が街へ出て、空を見上げ、深く呼吸をしていた。
アロマ・コープの株価は大暴落し、組織は解体された。
バーンズは失脚した。
彼がひた隠しにしていた自身の身体の腐敗臭が、皮肉にも彼を孤立させた。
俺は、リコの店の屋上で風を浴びていた。
「ねえケイン。次はどんな匂いを作るの?」
リコが新品の義手を見せびらかしながら聞く。
俺は、足元に咲いた一輪のタンポポを指差した。
「作らないさ」
「え?」
「もう必要ない。世界はこんなに、いい匂いで溢れてる」
俺は深く息を吸い込む。
泥と、排気ガスと、少しの希望。
それが、俺たちが生きる世界の、本当の香りだった。