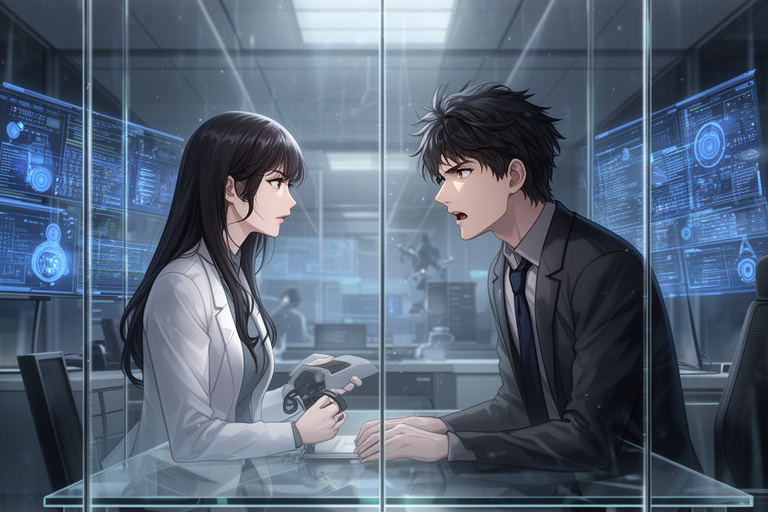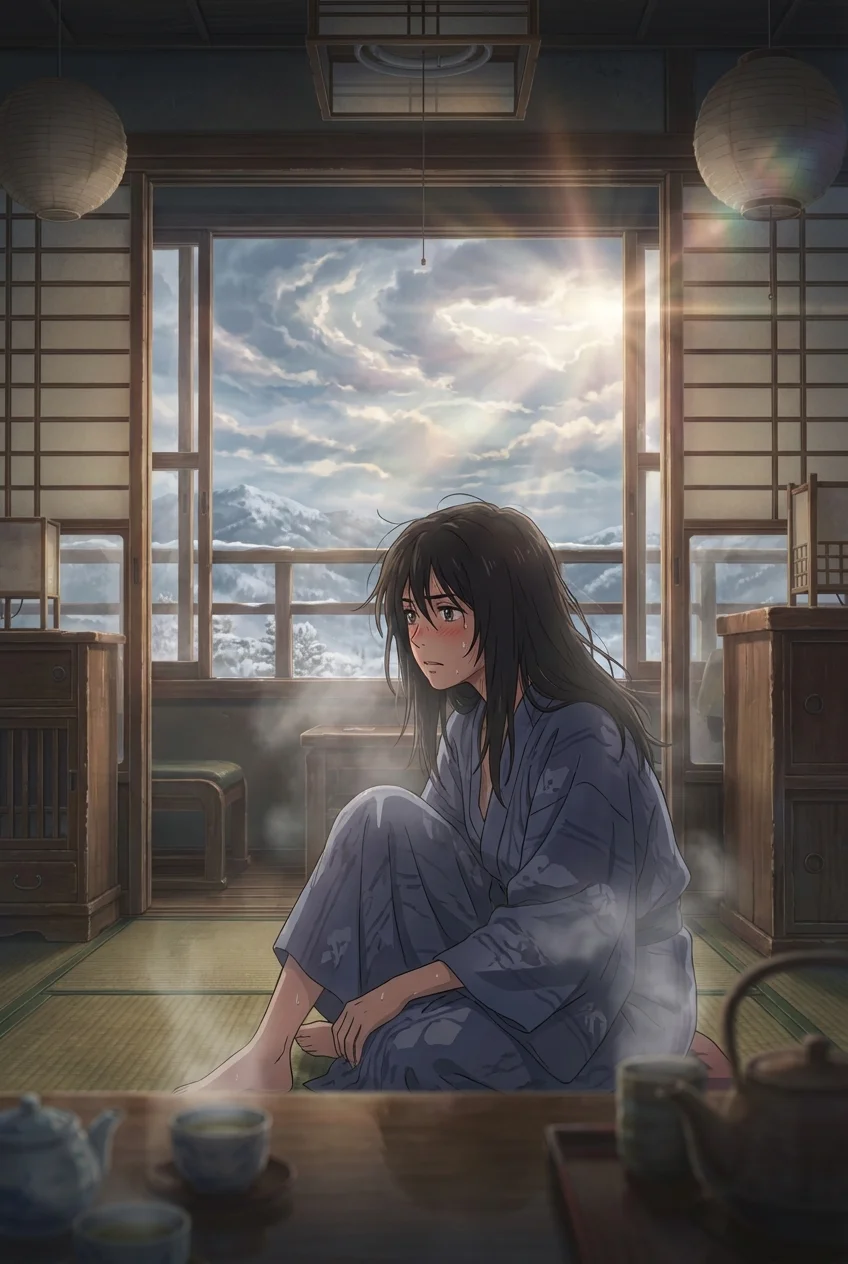第1章: 値踏みされる魂
氷雨。アスファルトが黒く、重く、世界を塗り潰している。
オークションハウスの裏口、湿った暗がりに一ノ瀬ミオはうずくまっていた。頬に張り付く亜麻色の髪、擦り切れた麻の作業着。肩口から覗く肌は病的なほどに白く、そこに散る無数の火傷痕だけが、かつて彼女が「修復師」であった証だった。染みついた墨と溶剤の匂い。鳶色の瞳は光を失い、足元の泥水に沈んでいる。
「……寒い」
物理的な温度ではない。魂の芯、その深淵が凍てついているのだ。師と仰いだ男の裏切り。被せられた億単位の負債。ミオの世界からは、とうに色彩が剥落していた。
――カツ、カツ、カツ。
水を踏む音。重厚で、傲慢なまでの響き。
顔を上げる。夜闇よりなお深い、濃紺のコートを纏う男。
レオニード・ヴァレンシュタイン。
氷河の銀髪が、街灯の灯りを冷たく弾く。瞳は極北の海を閉じ込めたアイスブルー。彼はミオを見下ろしていた。路傍の石ころとしてではない。ショーケースの裏に隠された、訳ありの宝石を見定める目つきで。
「君か。木島が壊した『聖母』は」
低く、甘く、鼓膜を震わす絶対的な声。喉が干上がり、声が出ない。
「指先から爪先まで、君の『所有権』は私が買い取った」
黒革の手袋が、ミオの泥にまみれた顎を掬い上げる。乱暴に、けれど陶磁器を扱うような不気味な繊細さで。
「立て。今日から君は、私のコレクションだ」
連れ去られたのは摩天楼の頂。雲を突き抜けるペントハウス、逃げ場なき硝子の城。
豪奢な浴室でメイドたちに磨かれ、皮膚のごとき薄絹(シルク)一枚を纏わされたミオは、広大な寝台へと放り出された。
現れたレオニードは上着を脱ぎ捨て、ベストのボタンを一つ、また一つと外していく。その仕草はまるで、厳粛な儀式のよう。
「……あ、あの、私、お金なら働いて……」
「黙れ」
ベッドの縁に腰掛け、彼が掴んだのはミオの手首。強くはない。だが蛇に睨まれた蛙のごとく、四肢が強張る。
抱かれる。そう覚悟して身を縮こまらせたミオの目に映ったのは、彼のポケットから取り出された宝飾用のルーペだった。
「肌の理(きめ)は悪くない。だが栄養失調による乾燥、劣化が見られる。早急な修復が必要だ」
「……っ、何を……」
「検品だ。贋作を掴まされる趣味はない」
冷たいレンズの縁が、熱を持った鎖骨を滑る。乳房の柔らかな膨らみ、肋骨の浮いた脇腹、そして太腿の内側へ。性的な愛撫などではない。ヒビを探す鑑定士の、無機質な視線。
屈辱で顔が沸騰する。いっそ獣のように貪られた方がマシだった。これほど冷徹に、ただの「物質」として吟味される行為は、ミオの人間としての尊厳を、カンナで削るように殺していく。
「素晴らしい」
感嘆の吐息。
レオニードの視線が釘付けになったのは、ミオの指先だった。薬品で荒れ、爪が短く切り揃えられた、職人の手。
ルーペが投げ捨てられる。彼は革手袋を口で噛んで引き抜き、素手でそのささくれた指を包み込んだ。
「この傷だらけの手こそが、君の真価だ」
関節の一つ一つに、崇拝のごとく唇が這う。
背筋を駆け抜ける、得体の知れない電流。恐怖? いや、違う。心の奥底で腐臭を放っていた「誰かに見つけてほしい」という歪んだ渇望が、カチリと音を立てて噛み合ったのだ。
第2章: 飼育される才能
時間は粘度を増し、蜜のように重く澱む。
レオニードの支配は完璧で、窒息するほどに甘美だった。
「口を開けて」
朝露に濡れた果実が、彼自身の指によって口内へ押し込まれる。咀嚼し、嚥下する喉の動きまで、あのアイスブルーの瞳は逃さない。
着替え、入浴、排泄のタイミングさえも管理下。許されたのは、アトリエでの修復作業のみ。
「君は世界で一番美しい道具だ。だから、君を直すのは私の役目だ」
作業中、背後から伸びる腕。耳朶を焼く熱い吐息。
レオニードの手が作業着の隙間へ滑り込み、敏感な蕾を弄る。だが、そこまで。
焦らし。
限界まで蜜を溢れさせ、脳髄が痺れるほど昂らせておきながら、決して絶頂(ごほうび)を与えない。
「……んッ、あ……レオニード様、おねがい……」
筆を取り落とし、床へ崩れ落ちる。乱れる呼吸、潤む瞳、理性の溶解。
冷ややかな笑み。彼はミオの目尻に浮かんだ涙を指で掬い、舐めとった。
「まだだ。その壺の修復が終わるまで、君に果てる権利はない」
罰と褒美の境界線が溶ける。
かつて「価値がない」と罵られ続けたミオにとって、この異常な執着こそが、逆説的な「生」の証明となっていた。
管理され、触れられ、見られることでのみ保たれる輪郭。
夜ごと繰り返されるのは、行為そのものよりも濃密な「観賞」。
様々な角度で固定され、肉体の陰影を、恥じらいに震える呼吸の揺らぎを、何時間も見つめられる。
視線だけで犯される。
その感覚に、ミオの子宮が甘く、疼き続けた。
「君は壊れているからこそ美しい」
呪いであり、福音。私は壊れていてもいい。彼が、そう望むなら。
第3章: 砕かれた硝子
平穏という名の檻。それが砕け散ったのは、ある午後のこと。
レオニード不在のペントハウスに現れた招かれざる客、木島剛造。
「随分といいご身分だな、ミオ」
脂ぎった顔、下卑た笑み。金無垢の腕時計が下品に光る。
「……帰ってください」
「帰れ? 誰のおかげでここで飼われていると思ってるんだ?」
木島はテーブルのワインを煽り、嘲笑と共に毒を吐いた。
「俺がお前に罪を着せた時、裏でシナリオを書いたのが誰か知ってるか? ……あのヴァレンシュタインだよ」
心臓が早鐘を打つ。耳鳴り。
「あいつはお前の腕に惚れ込んでいた。だが、まっとうな手段じゃ手に入らない。だから俺に金を渡し、お前を孤立させ、借金漬けにして……自分だけが救い手になれる状況を作ったのさ」
世界が反転する。
救済だと思っていたものは、巧妙な罠。
愛だと思い始めていた温もりは、計算尽くの所有欲。
ガチャリ。扉が開く。
戻ってきたレオニードは木島を見るなり、眉ひとつ動かさず部下へ合図した。ゴミのように摘み出される男。
残されたのは、凍りついた静寂。
「……嘘ですよね?」
掠れた声。
「私を騙していたんですか。私を壊したのは、あなたなんですか」
否定はない。コートを脱ぎ、歩み寄る男の瞳に罪悪感の欠片もなかった。あるのは、深淵のような独占欲だけ。
「それがどうした? 結果として君は私のものだ」
「ふざけないで!!」
叫びと共に、花瓶を投げつける。壁に当たり、派手な音を立てて弾け飛ぶ陶器。
その破片よりも鋭く、心は引き裂かれていた。
「私の人生を……心を、なんだと思ってるの!?」
レオニードの表情が消えた。
瞬時に詰められた距離。壁に押し付けられる背中。「鑑賞者」の仮面が剥がれ、そこには飢えた獣がいた。
「心? そんな不確かなものが何になる。私が欲しいのは君という存在そのものだ。君の才能、指、あげる悲鳴、その全てだ!」
「いや……離して! あなたなんて大っ嫌い!!」
拒絶。それが理性の留め金を外す引き金。
ビリッ、と絹が裂ける音が響く。
「ならば心が壊れるまで愛そう。二度と外の世界を望まないように、私の色で塗り潰してやる」
地獄の始まり。
優しさという麻酔なしの、生々しい執着の暴力。
逃げ場のない快楽の嵐が、ミオを飲み込んでいった。
第4章: 傷跡への口づけ
「……ぁ……あ……ッ」
空気の漏れるような喘ぎ。視界は白濁し、天井が回る。
連日連夜の、獣のごとき交わり。食事も喉を通らず、ただ貪られ続けた身体は限界を迎えていた。
高熱に浮かされ、アトリエの床へ倒れ込む。
抱き起こす腕。いつもなら冷徹なはずの彼の手が、微かに震えていた。
「ミオ……? おい、目を開けろ」
遠い声。
意識は暗い水底へと沈んでいく。
夢を見た。
誰かが泣いている。
暗い部屋の隅、壊れた玩具を必死に直そうとする銀髪の少年。
『直さなきゃ……直さなきゃ、捨てられる……愛されない……』
それはレオニードの記憶か。
完璧主義の怪物。傷ついたものしか愛せない、不器用な魂。
ふと、浮上する意識。
柔らかいベッドの感触。手の甲に落ちる、熱い滴。
薄目を開けると、そこには信じがたい光景があった。
あの絶対的な支配者が、ベッドの脇に跪き、ミオの荒れた指先に顔を埋めて泣いている。
「……すまない……死ぬな……壊れてしまう……」
無数の切り傷、薬品の火傷痕。祈るように落とされる口づけ。
支配ではない。崇拝でもない。
それは、懺悔。
「私は……傷ついたものしか愛し方がわからない。壊れかけの君を見て、初めて救われた気がしたんだ。だが、私が君を壊してしまったら……意味がない……」
仮面の下の素顔。愛に飢え、愛を恐れる、ただの孤独な男。
ミオの中で、何かが音を立てて繋がった。
被害者と加害者。修復師と破壊者。
二人は、欠けた茶碗の破片同士。互いの歪な断面がなければ、永遠に噛み合うことのできない、哀れな魂。
重たい腕を持ち上げ、銀髪に触れる。
「……馬鹿な人」
「ミオ……?」
「私を直せるのは、あなただけでしょう? ……泣いてないで、続きをなさい」
それは許しであり、新たな鎖。
第5章: 金色の契約
窓の外、黄金色の夕暮れが世界を燃やしている。
ミオはアトリエの椅子に座り、最後の仕上げを行っていた。
彼女が修復したのは、美術品ではない。レオニードという男だ。
扉が開く。入ってきた彼に、以前の威圧感はない。代わりに漂うのは、静謐で、けれど底知れぬほど濃密な執着の気配。
「体調は?」
「ええ。もう十分に」
立ち上がり、向き合う。純白のドレス。その首元には、彼が刻んだ紅い所有印(キスマーク)が、花びらのように咲き誇っていた。
「レオニード。新しい契約を結びましょう」
取り出した一つの指輪。
かつて木島が砕いた花瓶の欠片。それを「金継ぎ」の技法で繋ぎ合わせ、傷を芸術へと昇華させた指輪。
「私は逃げない。あなたの檻の中で生きてあげる」
彼の手を取り、その小指へとはめる。
「その代わり、私を一生、最高の作品として扱いなさい。傷一つ、涙一滴、あなたの許可なく流させないで。……私の全てを、あなたが背負うのよ」
奴隷契約に見せかけた、主人への宣戦布告。
レオニードは目を見開き、やがて美しく相好を崩した。瞳の氷が解け、狂おしいほどの熱情が渦巻く。
「ああ……契約成立だ、私の聖母(マドンナ)」
その場に跪き、ドレスの裾に口づける。そして這い上がるように腰を抱いた。
受け入れ、銀髪に指を絡める。
傷を金で継ぐように。二人の歪な愛は、背徳という漆で強固に結ばれた。
もう二度と、離れることはない。
壊れているからこそ、誰よりも強く、美しく。
悪魔の檻の中で、ミオは甘やかに、勝利の啼き声をあげるのだった。