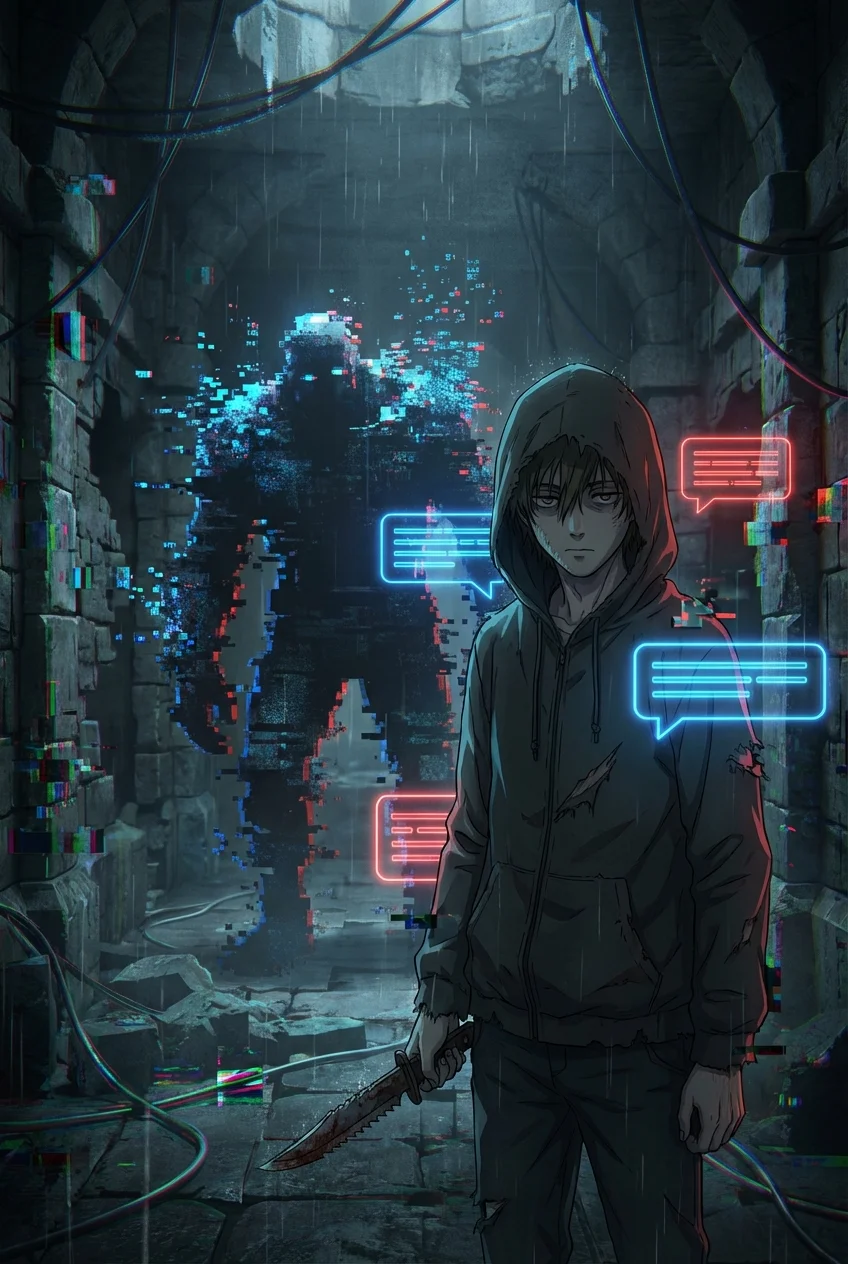第一章 未処理タスク:神格化
舌の根にへばりつく、酸化した微糖コーヒーの油膜のような後味。
それが、人間としての最後の感覚だった。
午前三時、東京都港区。
明滅する蛍光灯の下、キーボードを叩く乾いた打鍵音だけが、耳鳴りのように響いている。
「……これ、朝イチで……提出……」
視界が歪む。
積み上がった未決裁の書類の山が、白い雪崩となって僕に覆いかぶさってくる。
ああ、崩れる。
納期も、体裁も、僕の人生も。
次に瞼を持ち上げたとき、僕は物理的に雲の上にいた。
足元には回路基板のように幾何学模様を描く黄金の雲海。頭上には、エラーコードの青画面(ブルースクリーン)のような蒼穹が広がっている。
「天道効率(てんどう こうりつ)様。お待ちしておりました」
振り返ると、スーツ姿の男が立っていた。
背中から生えているのは翼ではない。無数のLANケーブルが束ねられ、羽ばたくたびに火花を散らしている。
「貴方様の神格化手続き、及びアカウント作成が完了しております」
「……は?」
僕は反射的に左手首を見た。
カシオのチープなデジタル時計。時刻表示は消え、『∞』の文字が点滅している。
「あの、すみません。私、無限残業ホールディングスの天道ですが。まだプレゼンの修正が」
「貴方様は過労死されました。しかし、生前の異常な『自己犠牲』と『タスク処理速度』が宇宙のデータベースにバグを引き起こし、神として採用されました」
LANケーブルの天使は、タブレット端末をタップしながら事務的に告げる。
「担当領域は『労働』および『潜在能力開発』です」
胃のあたりがキリキリと痛んだ。
死んでまで、採用。
死んでまで、労働。
手元には、愛用していたボロボロのシステム手帳があった。
ただ、その表紙は有機的な脈動を打ち、僕の血管と繋がっているような気味の悪さがあった。
勝手にページが開く。
『新規プロジェクト:世界の停滞打破』
『納期:なる早』
『報酬:存在の維持(※ノルマ未達の場合、魂の完全消去)』
「……なる早、かよ」
深いため息をつくと、口から白い粒子が漏れ出た。
どうやら僕は、天界という名の、究極のブラック企業にヘッドハントされたらしい。
第二章 赤字案件の再建
神になって一週間。
僕は下界の、とある寂れた商店街に降り立っていた。
古びた書店のレジカウンター。
店主の山田タカシ(45)は、曇った眼鏡の奥で、焦点の合わない目を虚空に向けている。
その手には、コンビニの安い焼酎と、開封されたカッターナイフ。
「いらっしゃいませ……なんて、言う気力もねえや」
山田が独り言ちる。
店の棚には、埃を被った名作たちが、墓標のように並んでいた。
僕は透明な身体のまま、カウンターに歩み寄る。
システム手帳を開く。
ズクリ、と心臓を鷲掴みにされるような激痛が走った。
神の権能を使う代償だ。僕の指先が、消しゴムで擦ったように少し透ける。
「痛っ……」
歯を食いしばり、痛みに耐えながら山田のステータスを解析する。
『ターゲット:山田タカシ』
『状態:絶望(自殺志願度85%)』
『スキル:売れない小説の執筆、過剰なまでの批判精神』
「小説家崩れ、か」
僕は山田の耳元で囁いた。声ではなく、思考のノイズとして。
『山田さん。なぜ、死にたいのですか』
「……うわっ!?」
山田が椅子から転げ落ちる。
周囲を見回すが、誰もいない。
『貴方の店が潰れそうなのは、客が本を読まないからじゃない。貴方が、売りたくない本ばかり並べているからだ』
「なんだ、お前……! 俺の何がわかる! 今のベストセラーなんて、全部ゴミだ! あんなの文学じゃねえ!」
山田がカッターナイフを振り回す。その切っ先が空を切る。
彼の怒り。それが、唯一の燃料だ。
僕は手帳のページを破り捨てた。
更なる激痛。喉の奥から鉄の味がする。
血の代わりに、光の粒子を吐き出しながら、僕は「現実」を書き換える。
奇跡なんて起こさない。ただ、彼の視界に「データ」を見せるだけだ。
山田のスマホが勝手に起動し、動画配信アプリが立ち上がる。
『吠えなさい、山田さん。その鬱屈したルサンチマンこそが、今の市場が求めるエンターテインメントです』
「……は?」
『貴方の毒舌は、美しい。そのカッターで自分を傷つけるくらいなら、世の中の駄作を切り刻め』
山田の手が震える。
彼はスマホの画面に映る、情けない自分の顔を睨みつけた。
そして、傍らにあったベストセラー小説を乱暴に掴む。
「……ああ、そうだよ。言ってやるよ」
録画ボタンが赤く点灯する。
「この小説の結末、ご都合主義すぎて反吐が出る。俺ならこう書くね――」
山田の声色が、半音上がった。
淀んでいた瞳の奥に、かつて文学青年だった頃の残り火のような熱が灯るのを、僕は見た。
カッターナイフは、もうテーブルの端に追いやられていた。
第三章 理不尽なトップダウン
「貴様か、現場のフローを勝手に弄っている新人は!」
雷鳴と共に、巨大な影が僕を覆った。
振り向くと、身長三メートルはあろうかという巨人が立っている。
「富」と「繁栄」を司る古参の神だ。
その手には、黄金でできた太い棍棒が握られている。
「人間どもには『宝くじ』という夢を見させておけばいいのだ! 余計な知恵をつけるな!」
ドォォォン!
棍棒が振り下ろされ、アスファルトが粉砕される。
僕は衝撃波で吹き飛ばされ、ガードレールに背中を強打した。
骨がきしむ音。
神体であっても、上位神の暴力は痛みを伴う。
「ぐっ……、非効率、ですね……」
「なんだと?」
巨人が僕の首を片手で掴み上げ、締め上げる。
視界が赤く染まる。
呼吸ができない。首の骨がミシミシと悲鳴を上げる。
「金を与えれば、人間は堕落し、また金を求める……。それは無限ループのバグだ……」
僕は霞む視界で、システム手帳を開いた。
残されたページは少ない。
使うたびに、僕の存在確率が削れていく。
だが、ここで引けば、あの日の社畜と同じだ。
「貴方様のやり方では、今後10年で信仰心が98%減少するというデータが出ています」
僕は手帳から溢れる光のグラフを、巨人の目の前に展開した。
「見ろ、この下降線を! 貴方が配っているのは『繁栄』じゃない。『依存』という麻薬だ!」
「うるさい! データなど知らん! 私は神だぞ!」
巨人が拳を振り上げる。
その拳が僕の顔面を捉える寸前、僕は最後の力を振り絞り、手帳に新たな一行を書き加えた。
『神々の業績評価制度:導入』
ピタリ、と巨人の動きが止まる。
彼自身の身体が、赤字(エラー)を示す警告色に発光し始めたからだ。
「な、なんだこれは!? 力が……抜ける……」
「貴方のコストパフォーマンスは最悪だ、と宇宙のOSが判断しました」
僕は首を離され、地面に膝をついた。
激しく咳き込むと、光る血だまりができた。
「物理攻撃で解決しようとするのは、無能な管理職の証拠ですよ」
第四章 最終プレゼン:辞表提出
巨人が膝をついたことで、神界に激震が走った。
僕はその隙を見逃さなかった。
手帳の全ページを一気に引きちぎる。
指の感覚が消えた。
右腕が肩まで透け、向こう側の景色が見えている。
この一撃を使えば、僕は消滅する。
「構わない。どうせ、死んだ身だ」
散らばったページが風に舞い、雪のように世界中へ降り注ぐ。
それは「天啓」ではない。
「通知」だ。
街中のサラリーマン、主婦、学生たちの脳内に、ポップアップウィンドウが開く。
『あなたの潜在スキルが見つかりました』
パン屋でレジを打っていた少女が、ふと手を止め、小麦粉で絵を描き始める。
満員電車で死んだ目をしていた男が、鞄からノートを取り出し、アプリの企画書を書き殴る。
「おい新人! 身体が……消えているぞ!」
巨人が驚愕の声を上げる。
「ええ。契約満了です」
僕は透き通っていく自分の手を見つめた。
不思議と、恐怖はない。
下界を見下ろせば、無数の「熱」が生まれている。
誰かに言われたからじゃない。
自分自身の意志で、人生というプロジェクトを回し始めた人々の熱気。
「あとは頼みますよ。これからの神の仕事は、願いを叶えることじゃない。彼らの邪魔をしないことです」
意識が白く溶けていく。
微糖コーヒーの不味い後味も、胃の痛みも、すべてが光の中に消えていった。
第五章 本業:ライフ・コンサルタント
「――失礼します」
重厚なマホガニーの扉をノックし、僕はその部屋に入った。
都心の摩天楼、その最上階。
「無限残業ホールディングス」、社長室。
窓の外には、かつて僕が身を投げ出したときと同じ、美しい夜景が広がっている。
だが、今の僕には、それがただの電気信号の羅列には見えない。
「誰だね、君は。アポは取っているのか」
巨大なデスクの奥で、男が顔を上げた。
充血した目。深く刻まれた眉間の皺。
かつての僕を、そのまま何十年も煮詰めたような、哀れな独裁者。
僕はスーツの襟を正し、一枚の名刺をデスクに置いた。
そこには『ライフ・コンサルタント 天道』とだけ記してある。
「御社の経営方針について、抜本的な改革案をお持ちしました」
「帰れ。コンサルなど不要だ。社員どもをもっと働かせる方法以外、聞く耳は持たん」
社長が手元の書類――恐らくリストラ候補者リスト――を握り潰す。
その手は、小刻みに震えていた。
「いいえ、救うのは社員ではありません」
僕は懐から、一冊の手帳を取り出した。
あの日、神界で使い果たし、そして新しく生まれ変わった革張りの手帳。
「救うのは、貴方だ」
「……なに?」
僕は手帳を開き、デスクの上に置かれた、枯れかけた小さなサボテンを指差した。
社長室に似つかわしくない、唯一の「生きた」もの。
「貴方の潜在スキルは『園芸』。そして『育成』だ。社員を数字として見るのをやめて、そのサボテンのように見てはどうですか」
社長の表情が凍りついた。
そして、ゆっくりと視線をサボテンに落とす。
その強張った肩から、力が抜けていくのが見えた。
彼は、悪魔ではない。
ただ、迷子になったまま大人になってしまった、悲しい子供だ。
「……君の入れたコーヒーは、飲めるのかね」
社長がポツリと呟いた。
「ええ。ただし、甘くはありませんよ」
僕はポットから、漆黒の液体をカップに注いだ。
湯気と共に立ち上る、深く、焦げ付くような香り。
社長がそれを一口啜る。
顔をしかめ、それから、ふう、と長く息を吐いた。
「……苦いな」
「ええ。それが、生きている味です」
僕は手帳を閉じた。
さあ、仕事の時間だ。
神様のアルバイトより、ずっとやりがいのある、人間の仕事が待っている。