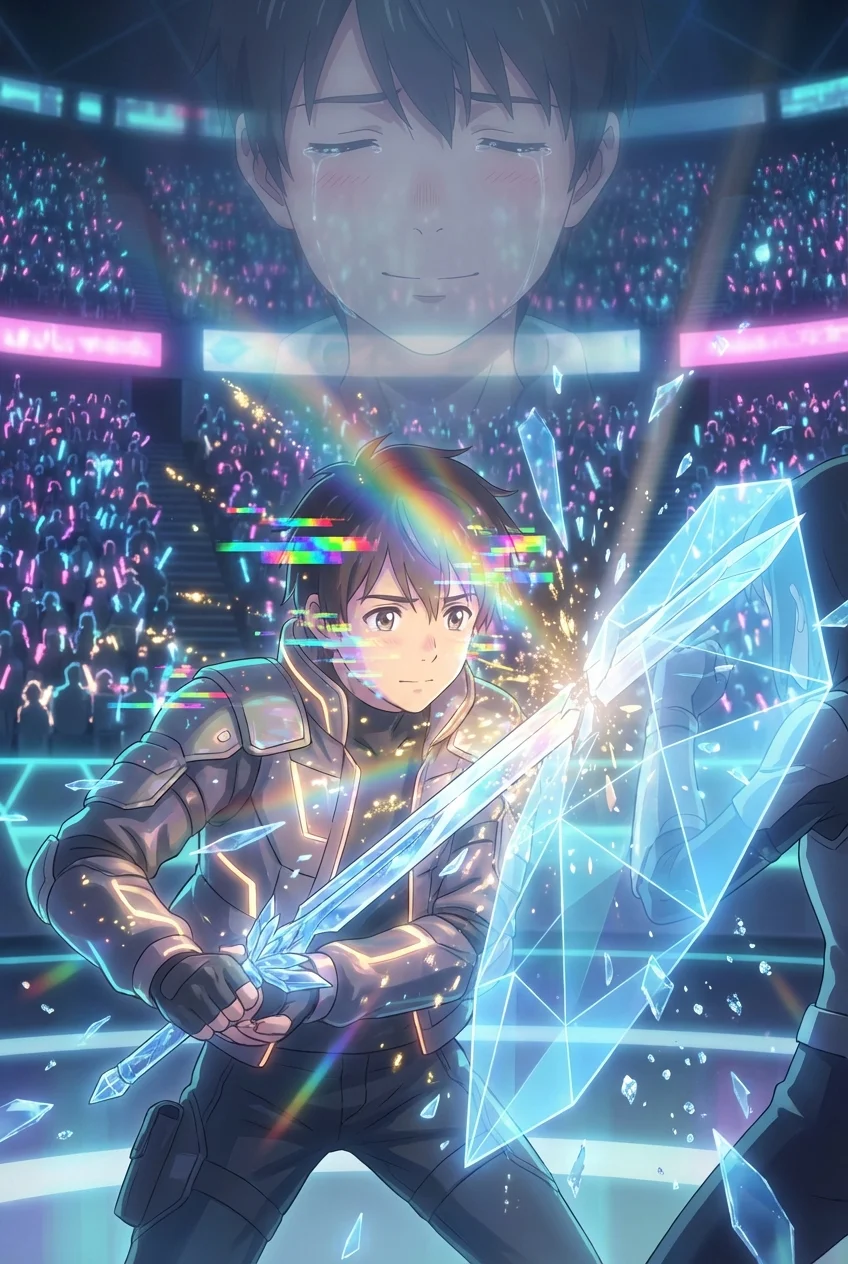第一章 錆びついた風の匂い
エルフの耳を隠すためのフードを、深く被り直した。
石畳を叩く靴音が、かつてとは違うリズムを刻んでいる。
八十年。
人間にとっては一生涯に等しいその年月は、私、シルフィードにとっては午睡のまどろみのようなものだ。
けれど、この街「王都アルカディア」にとっては、あまりに劇的な変化の時だったらしい。
「おい、道を空けな! 蒸気車が通るぞ!」
煤けた匂い。
馬の嘶きの代わりに、鉄と蒸気が唸る低い音が響く。
かつて彼――勇者レオンと共に凱旋パレードを行った大通りは、今や黒い煙を吐く機械仕掛けの車両が我が物顔で走っている。
「……うるさいわね」
小声で毒づき、人波を縫う。
私の見た目は、あの日と何一つ変わっていない。
銀色の髪も、透き通るような白い肌も、目元のほくろ一つさえ。
変わったのは、隣に彼がいないことだけだ。
『シルフィ、平和になったら何がしたい?』
ふと、記憶の蓋が開く。
草原の風。焚き火の爆ぜる音。レオンの少年のような笑顔。
『私は……そうね。静かな森で、本の整理でもして過ごすわ。人間の寿命は短すぎるもの。貴方がシワだらけのお爺ちゃんになる頃に、また会いに来てあげる』
『つれないなぁ。でも、約束だぞ。俺が爺さんになっても、絶対に俺のことを見つけてくれよ』
嘘つき。
視線の先、中央広場に聳え立つ銅像を見上げる。
剣を掲げた勇者レオンの像。
その顔立ちは美化されすぎていて、本人の愛嬌のかけらもない。
彼は、爺さんになることさえ叶わなかった。
魔王討伐の直後、原因不明の「魔力枯渇症」で、あっけなくこの世を去ったと聞かされた。
私はその時、極北の地で自身の魔力回復の眠りについていた。
目覚めた時には、葬儀どころか、彼の孫が生まれているような時代になっていたのだ。
「……約束、果たしに来たわよ。レオン」
花束はない。
彼が好きだったのは、花よりも団子だったから。
懐の紙包みには、老舗の和菓子屋で買ってきたみたらし団子が入っている。
その時だ。
広場の掲示板に群がる人々の話し声が、尖った耳に届いた。
「また出たらしいぞ、『王家の亡霊』が」
「墓所から毎晩、呻き声が聞こえるって話だろ?」
「騎士団も手が出せないらしい。近づいただけで、生気を吸い取られるとか……」
心臓が、早鐘を打った。
王家の墓所。
レオンが眠っている場所だ。
私は踵を返した。
宿に向かうつもりだった足は、自然と城の裏手、王家専用の霊廟へと向かっていた。
嫌な予感がする。
私の特異な才能である「魔力感知」が、彼の方角から、禍々しくも懐かしい気配を拾っていたからだ。
第二章 時を止めた代償
「立ち入り禁止区域です! これ以上は……!」
霊廟の入り口を守る若い衛兵が、槍を構えて私の前を塞ぐ。
彼の顔立ちは、どことなくレオンに似ていた。
垂れ気味の目尻や、困ると眉を寄せる癖。
「貴方、名前は?」
「は、はい? クレインですが……」
「そう。クレイン、下がりなさい。中で起きていることは、貴方たちの手に負えるものじゃない」
私はフードを外した。
月明かりに、銀髪がさらりと流れる。
露わになった尖った耳を見て、クレインが息を呑んだ。
「エルフ……? まさか、伝説の魔導師シルフィード様ですか?」
「伝説、ね。年寄り扱いしないでほしいけれど」
苦笑しながら、指先を軽く振る。
睡眠の魔法。
クレインは抗う間もなく、その場に崩れ落ちた。
彼を傷つけたくはない。レオンの血を引く子供なら尚更だ。
重厚な石の扉に手を触れる。
冷たい。
けれど、その奥から滲み出してくるのは、凍てつくような冷気と、そして狂おしいほどの熱量を持った「執着」だった。
「……開け(アペルト)」
防衛結界が、私を主と認識して霧散する。
この結界の術式を組んだのは、八十年前の私自身だ。
扉が軋んだ音を立てて開くと、腐敗臭ではなく、防腐剤とドライフラワーの乾いた香りが鼻をついた。
石造りの階段を降りる。
かつて英雄と呼ばれた男が眠る、最深部の玄室へ。
カツン、カツン。
私の足音だけが響く。
地下深くに進むにつれ、空気の密度が変わっていく。
濃密な魔力。
それも、ただの魔力ではない。これは「呪い」に近い。
「……誰だ」
地の底から響くような、擦れた声。
広間の奥、棺の上に腰掛けている「影」があった。
暗闇に目が慣れる。
息を呑んだ。
そこにいたのは、勇者レオンの遺体ではなかった。
肉体は半ば透き通り、青白い燐光を放っている。
骨と皮だけになった腕が、錆びついた聖剣を杖のようにして体を支えていた。
「レオン……なの?」
震える声で呼びかける。
影がピクリと反応し、眼窩に宿る蒼い炎が私を捉えた。
「シル……フィ……?」
ガラガラと崩れるような音。
それは彼が立ち上がろうとした音だった。
「来るな! 俺を見るな!」
絶叫。
それと共に、強烈な衝撃波が放たれた。
私はとっさに障壁(シールド)を展開するが、あまりの威力に数メートル後退させられる。
「どうして……どうして死んでいないの? 貴方は八年前に寿命で……」
「死ねなかったんだ!!」
レオンが叫ぶ。
その姿は、英雄の威厳など見る影もない。
リッチ(死霊の王)へと変貌しかけた、哀れな怪物の姿だった。
「俺は……約束を守りたかった。お前が目覚めるまで。お前にもう一度会うまで……ただ、それだけのために、禁術に手を染めた」
彼の告白が、私の胸を鋭利な刃物のように抉る。
魔力枯渇症などではなかった。
彼は自らの魂を聖剣に結びつけ、肉体を魔力で無理やり維持し続けていたのだ。
人間としての死を拒絶し、化け物になってまで。
「馬鹿よ……大馬鹿よ、レオン!」
涙が溢れて止まらなかった。
長命種(エルフ)の時間感覚における「またね」が、短命種(ヒューマン)にとってどれほど残酷な言葉だったのか。
私は今初めて、その重さを知った。
第三章 硝子の心臓を砕く時
「帰ってくれ、シルフィ。今の俺は、生者の精気を喰らわなければ存在を維持できない。このままでは、お前まで……」
レオンが苦しげに胸を押さえる。
その胸部には、心臓の代わりに青白く光る魔石が埋め込まれていた。
あれが、彼の命を繋ぎ止めている呪いの核。
「嫌よ。帰らない」
私は一歩、踏み出した。
「近寄るな! 俺はもう、お前の知っているレオンじゃない! 食欲と殺戮衝動に支配された、ただの亡者だ!」
彼が剣を振るう。
衝撃波が壁を砕き、天井から粉塵が舞い落ちる。
本気だ。
私を遠ざけるために、彼は本気で私を殺そうとしている。
けれど、私には見えていた。
その剣筋が、わずかに泣いていることを。
「『Show, Don't Tell』……貴方が昔、私に教えてくれた言葉ね」
私は杖を捨てた。
魔力を練り上げる。
攻撃魔法ではない。彼を包み込むための、浄化の光を。
「言葉で説明なんてしなくていい。貴方のそのボロボロの体を見れば、どれだけ寂しかったか、どれだけ苦しかったか、全部わかるわよ!!」
「シルフィ……ッ!」
私は走った。
飛んでくる闇の弾丸を、障壁も張らずに紙一重でかわす。
頬を掠めた魔力が、肌を焼き、血が滲む。
痛みなんてどうでもいい。
彼の懐に飛び込む。
八十年ぶりの距離。
腐敗臭などしなかった。
そこにあるのは、懐かしい彼の魂の匂いだけ。
「捕まえた」
私は、彼の骨張った体に抱きついた。
冷たい。
氷のように冷たい体。
けれど、私の体温が伝わると、彼はビクリと震え、剣を取り落とした。
カラン、と乾いた音が響く。
「……あたたかい」
レオンの声から、狂気が抜けていく。
「ずっと、寒かったんだ。シルフィ。暗くて、寒くて……お前がいない世界は、俺には広すぎた」
「ごめんね。待たせて、ごめんね」
私は彼を見上げた。
蒼い炎だけだった瞳に、かつての人間の瞳の色が微かに戻る。
「レオン。もう休んでいいの」
私は懐から、短剣を取り出した。
ミスリル製の、かつて彼が私にプレゼントしてくれた護身用の短剣。
「貴方を怪物になんてさせない。貴方は私の、最高の勇者だもの」
レオンは、私の意図を悟ったようだった。
彼は抵抗しなかった。
むしろ、安堵したように微笑んだ。
骸骨のような顔で、けれど確かに、あの日の少年のような笑顔で。
「ああ……頼む。お前の手で、俺の時間を動かしてくれ」
「愛してるわ、レオン」
「俺もだ。ずっと……これからも」
私は短剣を突き立てた。
彼の胸にある、青白い魔石へ。
パリン、と。
硬質な音が響き渡る。
それはまるで、硝子細工が砕けるような、儚くも美しい音だった。
第四章 明日へ続く足跡
魔石が砕け散ると同時に、レオンの体は光の粒子となって崩れ始めた。
呪縛から解き放たれた魂が、本来あるべき場所へと還っていく。
「ありがとう、シルフィ」
最後に残ったのは、穏やかな声と、一陣の風。
私の腕の中は空っぽになった。
けれど、不思議と喪失感はなかった。
胸の奥に、確かな温もりが残っていたから。
地面には、錆びついた聖剣だけが遺されていた。
「……さようなら。いいえ、またね」
私は涙を拭った。
もう、泣かない。
彼が命を賭して守りたかったこの世界を、私は見て回らなければならない。
彼が見ることのできなかった未来を、私の記憶(アーカイブ)に刻み込むために。
霊廟を出ると、空が白んでいた。
朝焼けが、工場の煙突や並び立つビル群を照らしている。
変わりゆく世界。
「う……ん……」
入り口で眠っていた衛兵のクレインが、目を覚ました。
彼は慌てて起き上がり、私を見て目を丸くする。
「あの、貴方は……中の怪物は……?」
「怪物はもういないわ。いたのは、ただの迷子の幽霊よ」
私は微笑んだ。
朝日に照らされた私の笑顔は、きっと八十年前よりも少しだけ、大人びて見えたはずだ。
「さあ、行きましょう。朝ごはんの時間よ。美味しいお団子があるの」
私は一歩を踏み出す。
エルフの長い寿命は、時に残酷な呪いとなる。
けれど今は、それを祝福だと思える。
だって私は、彼の物語を誰よりも長く、未来へと語り継ぐことができるのだから。
風が吹いた。
煤煙の匂いの中に、懐かしい草原の香りが混じった気がした。
(了)